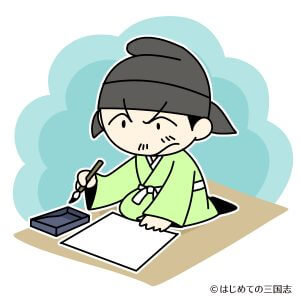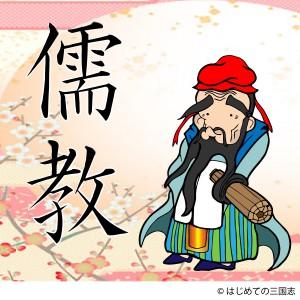
「子、曰わく…」という特徴的な書き出しで始まることが多い『論語』の言葉は、中学生の国語の教科書に必ずと言っていいほど取り上げられています。
中学時代、ツラツラと書かれている漢字の羅列を見て瞬時に拒否反応を起こし、それなのに暗記テストまであって大変苦労をしたという人もいるかもしれません。
「あんなもん何の意味があるんだ!」と罵る人も少なくありませんが、『論語』が日本に与えた影響は計り知れないほどなのですよ。というわけで今回は、『論語』が日本に与えた影響のほんの一部をご紹介したいと思います。
この記事の目次
百済の王仁(わに)が伝えた『論語』
(画像:王仁 Wikipedia)
日本に『論語』をもたらしたのは、5世紀頃に百済から渡来した王仁という人物であったと言われています。彼については『日本書紀』や『古事記』などにも記されており、『論語』だけではなく書の教科書と言われる『千字文』をもたらしたことでも有名です。
聖徳太子も『論語』の教えをリスペクト
『論語』に記されている内容は人として大切にするべき当たり前のことばかりですが、その当たり前をわかりやすい言葉で短く言い表しているということで学識のある人々に広く読まれるようになりました。
このように日本人の心を掴んだ『論語』の言葉は、ついに憲法デビューを果たします。「和を以て貴しと為し、忤うこと無きを宗とせよ。」
皆さんもご存知でしょう。これは、聖徳太子が定めた「十七条の憲法」の第一条です。ここに見える「和を以て貴しと為し」の部分こそ、『論語』学而篇から採用した言葉です。
「人とよく話し合って協力することを大切にしなさい」という意味のこの言葉は、聖徳太子が思い描いた理想の政治に必要不可欠なものだと考えられたのでしょうね。
仏教の解釈を『論語』の言葉で
中国では儒教が人々に大切にされていましたが、日本では儒教よりも仏教の方が人々に尊ばれていました。平安時代に一応科挙ができたものの、官吏でさえも世襲制度が横行していた日本では儒教を学ぶ必要性も感じられなかったのでしょう。
それでも、鎌倉時代に曹洞宗を開いた道元は度々『論語』の言葉を引用して仏教の教えを弟子に説いていたといいます。もしかしたらその頃には、『論語』の言葉は人々がわざわざ学ぶまでもないほど浸透しつくしていたのかもしれませんね。
江戸幕府も『論語』を奨励
表向きに『論語』を学ぶことが奨励されなくなってから長い年月が過ぎ去りましたが、そんな『論語』に再びスポットライトが当てられる時がきます。
それは、江戸時代です。江戸幕府は朱子学を官学として定めたため、朱熹が四書と称して尊んだ『論語』も日本人に広く学ばれることになりました。江戸時代には武士だけではなく、寺子屋で庶民の子や女の子も学問を受けたことから『論語』の教えは日本人なら誰もが知るものとなったのです。
中国人留学生も日本の『論語』教育に感動
やがて文明開化のときが訪れると、西洋の学問がもてはやされるようになって一時期『論語』の教えは日本人の心から消えかけてしまいますが、「和魂洋才」が唱えられるようになると、『論語』の教えは再びその息を吹き返します。
『論語』を大和魂と考えることに違和感を覚える人もいるかもしれませんが、その頃にはすっかり日本人の魂と同化していたのでしょう。この「和魂洋才」を実践した日本は、アジアで唯一西洋列強と渡り合える国に成長を遂げました。
日清戦争以降、中国人の日本留学が増えたのですが、日本を訪れた中国人留学生たちはびっくり。何せ中国ではとうの昔に読まれなくなった『論語』の教えが日本では未だに尊ばれていたのですから。
帰国後、中国人留学生たちがそのことを口々に話したために、中国でも『論語』が再び人々に読まれるようになります。その当時、西洋列強に虐げられていた中国ですが、アジアの同胞とも呼べる日本が、自国で生み出された『論語』の教えを矜持として西洋列強と渡り合っていると知ったときには、大変誇らしく感じたことでしょう。
三国志ライターchopsticksの独り言
『論語』の教えは現代を生きる私たちにも脈々と受け継がれています。『論語』そのものを学ばずとも知らず知らずのうちに親をはじめとする周囲の人々からその教えを学びとっています。
「日本人は宗教を持たないのに、なぜそれほどまでに礼儀正しく道徳の心があるのか?」と疑問に思う外国の人もいるようですが、その答えの1つとしてまず間違いなく『論語』の名を挙げることができるでしょう。我々日本人の道徳心の根源は『論語』にあります。そしてそれは、これから先も親から子へと脈々と受け継がれていくことでしょう。
関連記事:知らないと損をする!孔子に学ぶ健康法が参考になりすぎる!