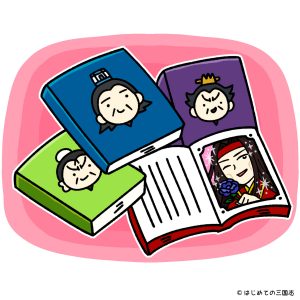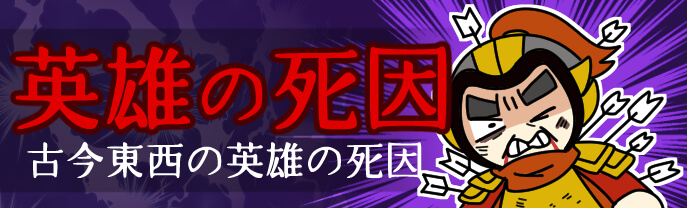三国志ってなにそれおいしいの?
そんな、はじめて三国志に触れる方に、小見出しをざらっと読むだけで、5秒で三国志がわかったような気分になれる〇三五三(ゼロから三国、五秒で三国)のコーナーです。
はじめて三国志に触れたとき、一番いらっとするのはなにかといえば、「名前が読めない」ことだと思います。
三国志を熟知されている方には、とてもまどろっこしいかと存じますが、このコーナーでは、なるべくふりがなをたくさんふりたいと思います。どうかご了承ください。
この記事の目次
三つの国の名前は、魏・呉・蜀
『三国志』は西暦200年頃、中国が三つの国に分裂して戦っていましたよ、という話です。その三つの国の名前が、魏(ぎ)と呉(ご)と蜀(しょく)です。
魏は、中国の華北地帯を治め、人口は2千600万人あまり。
呉は、長江以南の地帯を治め、人口は1千数百万人あまり。
蜀は、現在の四川省のあたりを治め、人口は数百万人あまりでした。
規模の違いは歴然としています。言ってみれば、日本の本州が魏で、九州が呉で、四国が蜀のような感じです。
三人の君主の名前は、曹操・孫権・劉備
魏の君主は曹操(そうそう)
魏の君主といえば、曹操です。
曹操で、押さえておきたい言葉は、「治世の能臣、乱世の奸雄」です。
意味は、「平和な世の中ではただの優秀な臣下だが、戦国時代のような乱世であれば、のしあがる危険な人物」ということです。
関連記事:曹操には弱点はないの?
呉の君主は孫権(そんけん)
呉の君主といえば、孫権です。
孫権で、押さえておきたいことは、孫家の三代目ということです。
呉は、孫権の父、孫堅の代から始まり、兄、孫策を経て孫権の代になります。父子で名前の読み方が一緒で混乱しますが……中国語では同じではないようです。
関連記事:陳寿が語る孫権像
関連記事:何でこんなに孫権は地味なの?
関連記事:本職より美味いカボチャを作った農夫・孫権
蜀の君主と言えば劉備(りゅうび)
蜀の君主といえば、劉備です。
劉備で、押さえておきたいことは、「桃園(とうえん)の結義」です。三国志演義では主人公でもあります。
関連記事:若い頃の劉備はチャラすぎ!劉備略年譜
関連記事:滅びゆくものへの郷愁劉備という生き方
関連記事:主人公になるべく登場した男、劉備玄徳
桃園の結義
若いころ、意気投合した劉備・関羽・張飛の三人が、義兄弟の契りをかわし、「生死を共にしよう」と誓いあうことです。
関連記事:歴史上最も有名な義兄弟の誕生!桃園の誓い
関連記事:涙なしには語れない桃園の結義
関連記事:ちょっと悲しい桃園三兄弟(劉備・関羽・張飛)の最期
三国志と言えば赤壁の戦い
西暦208年、魏の曹操が呉の孫権の支配地域の江東・江南地区に侵攻してきました。
圧倒的な国力を誇る魏との戦いを前に、孫権と劉備は手を組み、ともに赤壁という場所で曹操を迎え撃ちます。赤壁は、現在の武漢から長江を100キロほどさかのぼったあたりです。
この海戦では、呉の周瑜と蜀の諸葛孔明が策略を巡らして魏軍を火攻めにし、魏の大軍を呉・蜀連合軍が見事に破りました。
この戦いを赤壁の戦いといいます。三国志の中でも最も有名な戦いのひとつです。
三国志は一体誰が天下を取るの?(kawa註)2018/11/15追記
三国志の中心人物が、劉備、曹操、孫権が分かったところで三国で誰が天下を統一するのかお教えします。
普通に考えると、一番、支配面積が多い曹操の魏のように思えますよね。でも、答えはブーなのです。
じゃあ、劉備、孫権?残念ながら全部外れです。三国志の勝者になるのは、魏の曹操の部下である司馬懿という男です。
この司馬懿が、蜀の諸葛孔明を倒すなどして魏の政権の中でのし上がっていきます。
さらに、司馬師、司馬昭という息子達が司馬懿の功績を受け継いで権力を伸ばし、とうとう司馬懿の孫の司馬炎の時代に、曹操の魏を乗っ取って晋という国を建国します。
そして、蜀も呉も滅ぼしてしまい三国志は終わってしまうのです。
なんだか、煮え切れないグダグダな話だと思いますよね?でも、歴史の事実なので仕方がないのです。
三国志初心者の方は、三国志を統一したのは、魏の曹操の部下だった司馬懿の孫の司馬炎。このように覚えて下さいね。
三国時代の都はどこ?(上海くじら註)2019/8/4追記
現代中国の大都市を挙げるとすれば、「北京・上海・深圳」でしょう。共通点はいずれも海沿いということです。
しかし、三国時代の都と言えば「洛陽・建業(現在の南京辺り)・成都」と内陸ばかりです。歴史の教科書のページをめくって、頭にクエスチョンマークが浮かんだ読者もいるでしょう。しかし、これはごく自然なことで、メソポタミア文明と同じように中国でも黄河や長江といった川を中心に文明が発達したからなのです。ヒトの生命維持に必要不可欠なものは「水」。
生活する上でも物資を運ぶ上でも水(運河)は重要だったのです。北京と杭州に間に運河を引いたのはそのため。陸を馬で行くより、運河を船で行った方が早かったのです。
ちなみに唐の時代に留学した空海は寧波から中国に入り、杭州まで陸路で行き、杭州からは運河で北へと向かっています。当時(西暦200年前後)は現在ほど交通網が発達していませんでしたから、大国といえどもそれほど遠くの国と交流することはありませんでした。
曹操のいた魏も交流があったのは遠くても金印を授けた「クシャーナ朝」や「邪馬台国」ぐらいです。さらに古代中国では「中原」を制すれば、中国を統一したみなされます。中原とは洛陽や長安(西安)周辺を指す古い言葉で古代中国の中心を指していました。
現代で言えば「首都圏」みたいなニュアンスでしょうか。そのため、古代中国の武将は中原を制することを常に目的としていました。現在、発展している上海辺りは小さな漁村に過ぎなかったのです。三国志を読む場合は、古代中国の中心が現在のそれと大きく異なることを意識するいいでしょう。
後漢の最後の皇帝は誰?
実は三国時代は嵐のように突然やって来た訳ではありません。その前に「後漢」という王朝があり、それが崩壊したことによって三国時代へと突入します。実は曹操も孫堅も後漢の大臣だったのです。
しかし、漢王朝は日本に「漢字」をもたらし、非常に文明の発達した国家でした。最終的には宦官(去勢された公務員)や外戚(皇帝の親戚)の対立で徐々に国力を失います。後漢のラストエンペラー・劉協は悪玉・董卓によって皇帝にまつりあげられ、好きなように政治を行わせてしまいます。
実際に劉協よりも董卓の方がパワーがありましたから、仕方なかったのでしょう。それ以前に後漢王朝は深い問題を抱えており、皇帝はほとんどが20歳未満で即位高卒でいきなり大企業の社長をやるようなものです。
宦官や外戚が裏で朝廷の糸を引いていたことは明らかでした。皇帝は幼いですから、まだ政治に関する知識も経験も乏しいのが実情。策謀によって皇帝が操られてしまうのは必然でもあったのです。
曹操は皇帝だったの?
中国には曹操にまつわる故事成語(曹操の話しをすれば曹操が来る。転じて「噂をすれば影」)もあるほど有名な人物ですが、残念ながら曹操は皇帝にはなりませんでした。しかし、後漢の大臣の中でもメキメキと頭角を表し、後漢政府に不満を抱いた庶民の反乱(黄巾の乱)を平定し、兵士の数をぐんぐん増やしました。
対立した同じく大臣の袁紹を討ち取り、後漢のラストエンペラー・劉協を「許昌」の地へと迎えます。皇帝の住むところが「都」ですから、実質的に後漢の都は長安から許昌へと移ったことになるのです。長安の前の都は洛陽でしたから、後漢は一つの王朝の間に都を二回も変えたことになります。
こうした事実だけを取り上げても後漢王朝が砂上の楼閣であったことは一目瞭然です。さらに曹操は「丞相」という役職を名乗ります。丞相とは大臣の中でもトップを意味し、現在の内閣総理大臣のような存在です。
皇帝の劉協は経験が乏しかったので、実際には曹操の思いのままだったのでしょう。そういった意味では後漢の皇帝は曹操であるも同然という有様でした。
魏の初代皇帝は誰?
魏といえば曹操のようなイメージが浮かびますが、魏の初代皇帝は曹操の子である「曹丕」でした。曹操が生きている頃から「副丞相」として任務を執り、曹操の留守を預かるようになります。
やがて、父・曹操が天に召されると皇帝・劉協に皇帝の座を譲るよう迫るのです。裏では脅迫同然で帝位を奪ったのですが、表向きは皇帝が帝位を譲ると言い、一旦曹丕が辞退するなどの演技がありました。そして、大臣が曹丕に「皇帝からのお願いだから辞退してはもったいない」と言って、渋々皇帝の位を授かるという形をとっています。
この瞬間、後漢王朝は滅亡し「魏王朝」が成立。皇帝は曹丕となります。なお、国名を「魏」に変えた時点で二つの国家は全く別物であることを意味します。つまり、後漢が滅びなければ、ただ劉協が皇帝の位を後継者に譲るだけで終わりますが、この場合は国名も変わっているので後漢王朝は滅亡ということになるのです。
やがて、曹丕は何度か「呉」に攻め込んだ後、肺炎で亡くなっています。曹丕は後漢で宦官が権力を持ちすぎたことを憂慮して、魏王朝では宦官は一定の地位までしか出世できないシステムを作りました。
ところが司馬懿の待遇をよくしすぎてしまったことから、反対に司馬一族が権力を握るようになります。こうして魏は司馬一族によって滅ぶのです。
劉備はどうして皇帝と称したの?
曹丕が皇帝を名乗ると「我こそは漢王朝の末裔である」とばかりに劉備も皇帝を自称します。自称ですから、誰でもいいのですが、大臣らの信任を得た人物であると言えるでしょう。よく警察に捕まるとニュースで「自称〇〇」と出ますが、それとはだいぶ異なります。
かの劉備を犯罪者と同じにしてはいけません。明確な証拠こそ見つかっていませんが、劉備の家系をたどっていくと漢王朝の皇帝の誰かに行きつくのです。そのため、三国志演義では劉備をヒーローとして登場させています。
劉備は大臣らの薦めによって「益州」の地を取っていましたから、財源は豊富にありました。戦をするにも兵糧や武器の開発などでマネーは必要です。劉備のように肥沃な土地を持っていさえすれば、国土は狭くともリッチに暮らせるのです。
益州では「塩」や「鉄」が取れましたから、それらを国の専売として囲うことで安定した税収を確保できました。いわゆる「蜀漢ファースト」です。鉄というのは青銅よりも頑丈ですから、武器には最高のマテリアルとなります。
また、農機具も鉄にすることで作物の生産効率を高めることもできました。曹丕に比べれば、皇帝らしい事業を成したと言えるでしょう。しかし、関羽の仇討ちと称して進軍した際は呉に大敗を喫し、ほどなく平和条約を締結。
劉備が亡くなると蜀漢の政務は軍師・諸葛亮孔明に託されます。皇帝は子の劉禅が継ぎ、国家を繁栄させるために北伐によって資源を確保し、蜀漢を豊かにする政策を取ります。しかし、北伐はうまく行かず、朝廷内では劉禅と仲良しだった宦官・黄皓が暗躍し、蜀漢の宮廷は荒れ放題に。
その間に魏が攻めてきて蜀漢はわずか二代で滅んでしまうのです。
呉の孫権とは?
西の劉備とうまく関係を保ちつつ、長く政権を維持したのが呉の孫権です。父や兄を早くに亡くしましたが、周瑜や甘寧などのサポートによって孫権は江東の地を掌握します。曹丕が魏で皇帝となったとき、孫権はまだ力もなく、皇帝の配下になることにしました。
そして、魏の皇帝から「呉王」に任命されるという形を取り、魏と友好関係を保ったのです。実はこのとき、西の劉備が荊州の地を虎視眈々と狙っており、孫権は西と北から挟み撃ちされるのを恐れていました。
まずは、北の魏と主従関係になってから、西の劉備を抑えようと考えていたのです。案の定、劉備が攻めてくると弱点をうまく突いて撃退に成功します。こうして西から攻められる心配がなくなった孫権は表向き主従関係だった魏を裏切って、「呉」を建てます。
孫権が「魏」から独立したことで中国には一時期に「3名」の皇帝が存在するという過去に例を見ない事態となりました。皇帝が後継者争いで南朝と北朝に分かれることは多々あります。
しかしながら、三国時代のように違う勢力がそれぞれ中国の皇帝を名乗るという「三者鼎立」は非常にレアな状況と言っていいでしょう。そうしたジャンケンのような状態だったからこそ三国志は1800年近く経った今でも人気を博しているのです。
関連記事:超分かりやすい!三国志 おおざっぱ年表
関連記事:何から読めばいいの?三国志入門向けの小説と漫画を紹介!