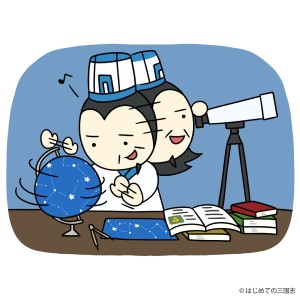学生の皆さんは長い夏休みですが、楽しい夏休みで唯一憂鬱なのは、提出しないといけない大量の宿題ではないでしょうか?
そこで今回のはじさんでは、偉人達の勉強法について紹介しますよ。皆さんの勉強のヒントになったらいいですね。
勉強は広く浅くがモットーな諸葛亮孔明の勉強法
三国志の英雄、諸葛亮孔明(しょかつ・りょう・こうめい)は、若い頃から勉強法もかなり違っていました。当時の勉強とは、丸暗記が基本で、一冊の本の内容と注釈を隅から隅まで覚えるのが普通でしたが、孔明は、それを面倒くさいと感じていて一冊の本を一通り読んで、大体の内容を覚えると、次の本に移りました。こうする事で、孔明は同級生が一冊の本に必死になっている頃には、二倍、三倍の本を読んで、多くの知識を吸収できました。
孔明の知識は、儒教だけではなく、天文や土木、法律などの様々な分野に及んでいますが、それは広く浅く勉強をした事によって得られていたのです。
孔明は、学問のポイントをよく知っていて、それさえ覚えれば、後は捨ててもいいという見極めが上手い人だったのです。
バルチック艦隊を破った、秋山真之(さねゆき)の勉強法
日露戦争のハイライト、日本海海戦において世界最強の艦隊と言われたロシアのバルチック艦隊を撃滅した日本海軍の参謀、秋山真之も、独特の勉強法で、知られる人物でした。彼は海軍兵学校時代、クラスメイトが必死にテスト勉強をする中で、余裕の顔をして遊んでいましたが、いつでも成績はトップクラスでした。不思議に思った仲間が理由を聞くと真之は、こう答えました。
「テストというのは、教官がどうしても生徒に覚えてもらいたい事を出すそれは急に増えたりはしないんじゃから、過去に出された四、五年分のテストを集めてきて、それを読んでいれば、大体の試験範囲は分かる後は、そこだけ勉強して、残りは遊んでおればいいんじゃ」
この要領の良さで、真之は常に学年でトップクラスであり続けました。ただ、これにしても、入念に過去問を解いて教官の出題傾向を予想し外さないだけの観測力は必要になります。やはり、秋山真之は日本海軍最高の頭脳と呼ばれるだけの事はあったのです。
本は声に出して読め! 緒方洪庵(おがた・こうあん)
日本では、古来、学問とは素読(そどく)で行われていました。素読とは、意味が分らなくても、まず読んで声に出す事です。かつて福沢諭吉も学んだ緒方洪庵の適塾では、オランダ語の初心者にも大声で音読させていました。
勉強は目で覚えるだけではなく、声も耳も使う事でその記憶力が高まると言われています。そして、人前で発音させる事で同時にスピーチ力も身に付くので、自分の意見を人前で発表する時にも上がらないで済むようになるのです。よく役者が台詞覚えを良くする為に台本を抑揚をつけて読み上げ、身ぶり手ぶりをつけたりしますが、あれも、この理屈と同じものなのです。
三国志ライターkawausoの独り言
これはkawausoが個人的にやっている勉強法ですが、全否定勉強法というものがあります。これから関心を持って調べようという事を全てマイナス面で捉えて全て否定する事で理解していくのです。一見すると、とても不毛で退屈な作業に見えますが、普通に調べるだけでは分らない意外な裏などが出てくる事もあり調べている対象に関係する理解に深みが出てくるメリットがあります。
もちろん、こちらを応用した全肯定勉強法で、世間では評判の悪い事柄をあえて全肯定してみて、隠されたメリットを探り出す方法もあります。もし、卒論などの進め方、テーマに困っている方がいたら、上のやり方を参考にしていただければ、かなり意欲的な論文が書けるかも知れませんよ。本日も、三国志の話題をご馳走様・・
関連記事:本当に病弱?実は健康に自信があった孔明、寿命を縮めた大誤算とは?