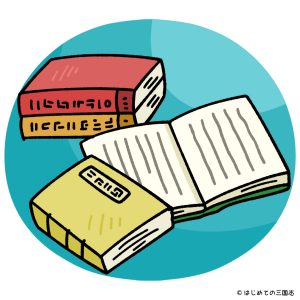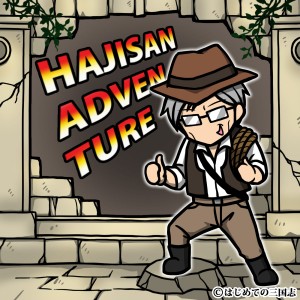三皇五帝よりも前の時代、天地開闢(てんちかいびゃく)、すなわち天地創造を起こしたとされる神、盤古。
現代では、その存在は三皇五帝の神話の成立後、後漢以降の時代に新たに神話として確立したと考えるのが定説になっています。
しかし、我々HMRは独自に調査を進め、盤古の天地開闢神話と、古代中国における宇宙観にははっきりと親和性があるという事実を見出しました。
やはり、盤古は中国最古の神であった!?今回はこの謎に迫ってみたいと思います。
この記事の目次
古代人が想像した宇宙の構造……宇宙観ってなに?
科学技術が発達するよりもはるか以前の時代から、人々は自分たちが住んでいるこの世界、ひいては宇宙全体がどのような構造をしているのか、それを想像し続けてきました。
古代インドには、宇宙は天と空気と大地の三層で構成され、それぞれの層がさらに3つの層からなるという全9層の宇宙観がありました。
とぐろを巻くコブラの上に巨大な亀が乗り、更にその上にいる象が大地を支えているというイメージ絵を見たことのある人も多いでしょう、古代バビロニアには大地の端を巨大な山脈が囲っており、その上をドーム状の天が覆っているというまるで宇宙全体がひとつの巨大な建造物であるような宇宙観が存在していました。
私達が学校で学ぶ古代の宇宙観としては古代ギリシアの数学・天文学者であったプトレマイオスが体系的に確立した、地球を中心とした宇宙観「天動説」が馴染み深いですね。
地球は球形であると考えるのが当たり前のように思われるかもしれませんが、現代においても地球は球形ではなく平面状の構造であると信じる人もおり、カリフォルニア州に本部を置く「地球平面協会」が今でも活動を続けています。
漢の時代、中国には3つの宇宙観が存在した!?
古代中国には「天円地方」という宇宙観が存在しました。「天円地方」に関する記述は、前漢の武帝の時代に編纂された思想書、『淮南子(えなんじ)』に見ることができますが、その考え方自体は紀元前5000年から3000年頃には存在していたとされます。
「天円地方」とは、四角い大地の上に、円盤状の天が存在しているという宇宙観です。なぜ、四角い大地の上に円状の天があるのかというと、星々が北極星を中心に円を描くように動くことから、円形をした天が回転していると考えられたためです。世界遺産にも登録された北京市にある史跡「天壇」(てんだん)は1420年に明の永楽帝が祭祀を行う場として建立した建造物ですが、天円地方をモチーフとした円形の構造を特徴としています。
ちなみに、この「天円地方」の宇宙観は日本にももたらされており、その痕跡は「前方後円墳」と呼ばれる古墳の形状に見ることができます。(鍵穴のような形をした古墳の四角い前部分が「天円地方」における地を意味し、後部の円形部分が「天」を意味しています)
漢の時代になると、この「天円地方」の考え方から派生した3つの新たな宇宙観が成立しています。
- 蓋天説(がいてんせつ)
「蓋天説」は「天円地方」の考え方を最も直接的に受け継ぐ宇宙観で、円形の大地の上空に円形の天が存在するというものです。
「蓋天説」では、太陽は天の端にあって、天が回転するとともに移動しており、その光が届く範囲が昼、その範囲を出た場所が夜になると考えられました。
- 渾天説(こんてんせつ)
「蓋天説」では、天体の動きに説明がつかないことが多く、これを修正する形で、より実測される天文の動き即した宇宙観として成立したのが「渾天説」です。渾天説に関する、最も重要とされる文献は、かの後漢時代の天才科学者こと張衡(ちょうこう)が記した書物にあります。
その記述によれば、天は卵の殻のように地を覆うように存在し地はさながら卵黄のようにその天の中心に位置しています。地の水平線の下(天の半分下)には水が満ちており、天そのものは地上から見て天頂(真上)から北に36度傾いた軸を中心に回転しています。
この宇宙観は、張衡が天文観測のために発明した「渾天儀(こんてんぎ)」(西洋の天球儀とほぼ同様のもの)に基づいて考えられており、水平線や赤道、子午線という概念が導入されています。古代ギリシアの「天動説」に近い宇宙観と言えるでしょう、
- 宣夜説(せんやせつ)
三国時代の後、東晋時代の人である虞喜(ぐき)が、歳差(さいさ)と呼ばれる現象を発見します。歳差とは、自転している回転体の軸が円を描くように振れる現象を指すことばで、「みそすり運動」などとも呼ばれます。歳差現象を渾天説に当てはめるなら、天の回転軸は円を描いて振れねばならず、結果として天が一体のものとして規則性のある運動をするのはおかしいと結論づけたのかもそれません。
その虞喜が提唱した宇宙観が「宣夜説」です。「宣夜説」では、宇宙を「蓋天説」や「渾天説」のような明確な形態を持ったものではなく、ただ永遠に広がる虚空であるとしています。地上から見た夜空の漆黒も、海の色が見方によって変わるのと同じく宇宙本来の色ではなく、星々も天に張り付いてその回転に合わせて動くのではなく、それぞれ勝手に虚空に浮かんでいて独自の運動をしているものとされました。宇宙を無限に続く空間と捉える「宣夜説」はある意味で現代科学における宇宙論と親しいとも言えますが結局多くの人に支持されることなく、衰退してしまいます。
「天然地方」こそが、盤古の天地開闢神話が最初にあった証拠!?
漢から東晋の時代にかけて。さまざまな宇宙観が考案されましたが、文化的に最も大きな影響を持っていたのは最も古くから存在した「天然地方」であると言えるでしょう。それは明代に建設された「天壇」が「天然地方」の思想に基づいていることからも伺えます。
そして、この「天然地方」の宇宙観に皆さんは既視感を感じないでしょうか?そうです!!あの盤古による「天地開闢神話」です。はじめ、この世界の天地はピタリと合わさっていたものをその間に生まれた盤古が18000年の歳月をかけて成長、ジリジリと天を地から切り離していき、ついに完全にその二つを分離したという「天地開闢神話」。
天と地が分かたれ、その間に空間があるとする「天然地方」の宇宙観は、まさに盤古によって創造された宇宙そのものではないですか!!この中国最古の宇宙観と、盤古の神話との間に見られる親和性。これが、盤古の存在が天地創造の神として最初に語られた神話でなくて、一体何であるというのでしょうか!!我々HMRは今後も盤古の神話の謎に、鋭く切り込んでいく予定です。
「はじ三」トンデモライター・石川克世のぼやき
……まあ、むしろ「天円地方」説に基づいて、周辺国から流入してきた神話・伝承をベースに後付けで盤古の神話が創られたそう考える方が、自然なんですけどね(自爆
しかし、まだまだ「盤古」の神話には謎が多く残されているのも事実です。あらたな情報がすべてを覆す可能性だって……。ともあれ、次回にご期待ください。」
関連記事:2300年前の古代中国に動物園が存在した?キングダムに登場するランカイのモデルも?
関連記事:竜にも階級があった!?某国民的・神龍が登場する漫画は中国史に忠実だった!