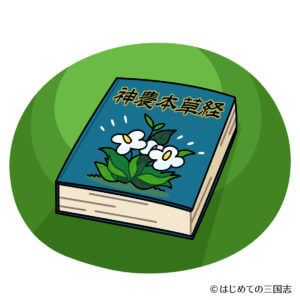『三国志』でしばしば登場する天才ドクター・華佗。かれの天才ぶりは一千年以上もの時代を先取りして全身麻酔薬を施した上で外科手術を行っていたというほど。ブラックジャックも顔負けの天才外科医・華佗が発明したとされるその麻酔薬の名前は「麻沸散」と呼ばれています。この「麻沸散」とはいったいどのような麻酔薬だったのでしょうか?
麻沸散は大麻?
痛みを感じる神経を麻痺させることによって患者の精神的苦痛を取り除くことができる麻酔薬。麻酔薬といえば、アヘンや大麻といった植物が思い浮かびます。現代では麻薬として取り締まられてはいるこれらの植物も、遠い昔には薬草として活躍していたのです。アヘンや大麻が経口で摂取されていたことや、また麻沸散に「麻」の字が使われていることなどから、華佗の麻沸散は大麻であるとの説が唱えられています。
更に、後漢時代に成立した『神農本草経』という薬物事典に大麻が登場していることもその説の裏付けとして挙げられています。しかし、大麻ではないのでは?という異論も唱えられているようです。
麻沸散は朝鮮朝顔?
どうやら、麻沸散の「麻」は大麻というわけではないようなのです。「麻沸」という「混乱して滅茶苦茶になる」という意味の熟語があり、華佗の麻酔薬は飲むと混乱して意識を失うことから麻沸散という名がつけられたという説もあります。大麻ではないのなら、一体何なのか?
世の学者たちは麻沸散の主な原料は朝鮮朝顔なのではないかと疑っているようです。この朝鮮朝顔について、明代に著された『本草綱目』には熱い酒に混ぜて患者に飲ませると、手術する際に患者は痛みを感じなくなると記されています。また、その他諸々、麻酔薬について説かれている書物には、朝鮮朝顔の別名「曼陀羅花」の4文字が記されていることが多い様子。これらの記述に鑑みると、麻沸散も朝鮮朝顔を主成分としていたのではないか?と思えてきますね。
江戸時代に発明された「通仙散」
実は、華佗が発明されたとする麻沸散にヒントを得て、世界で初めて全身麻酔薬を発明した人が江戸時代の日本にいたのです。その人の名は華岡青洲。
彼は、とある書物に「麻沸散の調合には朝鮮朝顔を用いる」とあったことだけをヒントに試行錯誤を繰り返し、自分の母親の命や妻の視力という大きな犠牲を払い、ついに全身麻酔薬「通仙散」を発明。更に、彼は全身麻酔を施した女性の乳がんを切除することに成功します。しかし、朝鮮朝顔を主成分とするこの強烈な麻酔薬は大変危険なものであると華岡自身がよくわかっていたようで、秘伝のものとされ数少ない弟子のみが受け継ぐことができたのでした。
なぜ華佗の麻沸散は後世に伝えられなかったの?
もし、麻沸散の主成分がやはり朝鮮朝顔だったとしたら、華佗も華岡青洲と同じようにその危険性をわかっていて、わざと弟子に伝えなかったのでしょうか?その答えは「ノー」だったようです。華佗は自らの技術を後世に伝えるべく、『青嚢書』という医学書を著していました。ところが、その書物が世に出ることはありませんでした。それはなぜか?華佗は曹操によって殺されてしまったからです。
持病の頭痛に悩んでいた曹操は、華佗をかかりつけの医者として迎えます。しかし、儒学が重んじられていた当時、医者の地位というものはそれほど高くありませんでした。医術というものは何やら仙術の一種だと思われていたのです。どれほど尽くしても待遇が改善されないことに嫌気が差した華佗は、妻が病気で倒れたと嘘をついて故郷に帰ります。ところが、その嘘はあっけなく曹操にバレてしまい、怒った曹操は華佗を投獄。
度重なる拷問でボロボロになり、自らの死を悟った華佗。なんとかして世に自らの医術を残したいと牢番に『青嚢書』を授けようとしましたが、罰を恐れた牢番はそれを固辞します。牢番に『青嚢書』を受け取ってもらえなかった華佗は、あろうことかその『青嚢書』を燃やしてしまったのでした。もしも、この『青嚢書』が世に残っていたら、もっとたくさんの命が救われていたかもしれませんね。それにしても、その『青嚢書』を燃やしているとき、華佗は何を思っていたのでしょうか?
※この記事は、はじめての三国志に投稿された記事を再構成したものです。
▼こちらもどうぞ