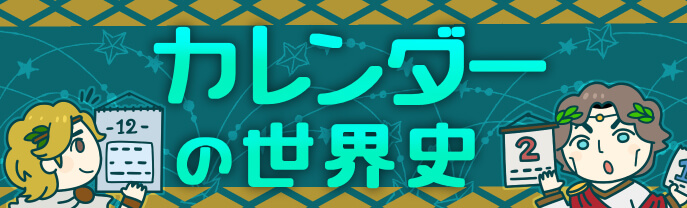オランダを代表する画家ヨハネス・フェルメール【1632年〜1675年】
その作風は「バロック絵画」と位置づけられ、主に「躍動感あふれる」という単語で表現されています。例えるなら、映画や演劇の中で動く人や情景を、一場面として切り取り、一時停止画像のように見せる作風と言い換えることもできるでしょうか。
近年の日本では、バロック絵画の画家の中でも、特に、このフェルメールの作品は人気が高いようです。今回は、フェルメールの魅力を探っていくための初回コラムとして、フェルメールの人生に注目したいと思います。どうぞご一読ください。
戦時下に描かれていたフェルメールの作品たち
まず、フェルメールの生きた時代のオランダは、どのような状況だったでしょうか?
ここからお話します。年表をみると分かることですが、「戦争」の時代だったということです。しかも幾度も複数の国々と戦争していたのです。具体的には、スペイン、イギリス、フランスです。いずれも、大国と呼ばれる国々と言えます。フェルメールが生まれる直前に遡りますと、当時は、スペインが世界中に植民地を作り、世界帝国を築いていました。オランダは、そのスペインの領土の一部でもありました。
しかし、そのスペインが、オランダとイギリスの同盟軍との間に起きた戦争「アルマダの海戦(1588年)」に敗北します。以降、17世紀前半には、入れ替わりで、イギリスが台頭しようとしていました。その頃にフェルメールは生まれました。
当時のオランダは、16世紀末〜17世紀前半にかけて行われた「スペインとの独立戦争(主に「八十年戦争」と呼ばれる)」により、独立を勝ち取り、さらに、アジア貿易による経済効果もあったという状況でした。経済的に好景気で、発展期だったのです。しかし、フェルメールが20代半ばの歳、若き画家として駆け出したばかりの頃、オランダの政治・経済的状況に、大きな変化がありました。「第一次英蘭戦争(1652年–1654年)」です。つまり、オランダとイギリスとの間の戦争でした。
この時期のイギリスは、「ピューリタン革命(1648年)」によって王政が中断され、共和制が敷かれ、「イングランド共和国」と呼ばれた時代でした。ただ、共和国の指導者の「クロムウェル」が「護国卿」として、実質的に独裁政治を敷いていた状況でした。さらに、対外政策として積極的に武力行使をしていたのです。
つまり、
スコットランド王国征服(1650年)
北アイルランド征服(1649年〜1650年)
このように着実に領土拡大を実現していたのです。
(※少し細かく言えば、「スコットランド王国」については、「1603年〜1648年」と「1661年〜1707」年の間は「イングランド王国」と「スコットランド王国」が「同君連合」と呼ばれ、一人の国王が二つの国の国主であった時代がありました。詳しくは、今後、イギリス史を特集する別の機会に記したいと思います。)
(話を戻すと)
そのクロムウェル指揮によるイングランドの侵攻で、現在の「イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)」の本土の基礎が、このときに出来上がったと言ってもよいでしょうか。
そして、1651年の「航海法」制定により、クロムウェルは、オランダに牙を向けたのでした。(※「航海法」とは、イングランドが自国の権益を守るためにオランダの貿易船がイングランド領内に入れないようにしたものとされています。)
それだと、オランダにとっては貿易による利益が減少するため、反発し、イングランドとの戦争に発展してしまったのです。結果は、オランダの敗北に終わります。すると、それまでオランダがインドなどのアジア地域との貿易を独占していた状況ではなくなりました。(実際は、戦争敗北によって、それほど大打撃を受けたというものではなかったとも言われています。)
しかし、好景気に衰えの兆しが見え始めたのは確かで、貿易バブルがはじけたようなものでしょうか。このように、オランダに暗雲が立ち込める不穏な状況下で、フェルメールは画家としてスタートしたのです。その後、フェルメールが43年の生涯を終えるまでの間、オランダは幾度も他国と戦争し続けていたのです。しかも、その結果は一進一退の状況で、オランダにとっては敗北もあり、確実な勝利と呼べる成果はありませんでした。
フェルメールの生活環境は?
フェルメール自身の生活環境ですが、こちらも安穏としたものではなかったようです。フェルメールの父は借金まみれだったそうで、フェルメール自身の生活は貧しかったそうです。しかし、1653年に、カタリーナ・ボルネスと結婚したことで転機が訪れたようです。妻のカタリーナの実家がお金持ちで、相当な援助があったため、絵画制作にも没頭することもでき、暮らせていけたとも言われています。
カタリーナとは20年にわたる結婚生活でした。その生涯を一人の女性に捧げるという、純愛を貫き通した夫だったという見方もできます。しかも、10人以上の子どもを授かったのです。(14人いて、内4人は死産だったという説が有力でしょうか。)しかしながら、見方を変えると、かなり出費がかさむ経済的には貧しい結婚生活だったようです。
さらに、フェルメールが、その生涯を通して住み続け、愛したという街が「デルフト」でしたが、この街で、火薬庫の爆発事故が起きたと伝わっています。(1654年のことです。)数百名以上もの死傷者を出したとも伝わっています。また、フェルメールが敬愛していたと言われる「カレル・ファブリティウス」という画家も事故の犠牲になったのです。そんな不安要素が増すばかりの状況でフェルメールは、絵を描き続けました。
こちらもCHECK
-
-
フェルメールは戦争を描いていた?「窓辺で手紙を読む女」に隠された歴史の暗号
続きを見る
「現実逃避」か、それとも「芸術療法」だったか?
しかし、生み出された作品たちは、「美」や「恋愛」を想像させるものが多い印象です。研究者の間でも、それはフェルメールにとっての「現実逃避」だったのではないかとも言われていますし、あるいは、精神を落ち着けるために、そうせざる得ない状況だったかとも推察されるのです。ある意味、「芸術療法」だったと言い換えることができるかもしれません。
ただ、フェルメールの絵画作品を幾つも眺めていると、現実逃避で描いたとは思えないと感想を持ってしまうのです。つまり、作品の中に、フェルメールが、生きる希望や社会への希望を持っていたと感じさせる場合もあるのです。
こちらもCHECK
-
-
印象派はどうして誕生したのか?300文字でしったかぶり
続きを見る
終わりに『窓辺で手紙を読む女』
次回は、フェルメールの作品で、大注目されている『窓辺で手紙を読む女』にスポットを当てて、お話します。お楽しみに。
>>フェルメールは戦争を描いていた?「窓辺で手紙を読む女」に隠された歴史の暗号
【主要参考書籍】
・『フェルメール 静けさの謎を解く』( 藤田 令伊 著 / 集英社新書)
・『フェルメール 作品と生涯』(小林頼子 著 / 角川ソフィア文庫)
・WEBサイト『アートの森』より《窓辺で手紙を読む女》(修正版)の紹介