
なぜ外戚と宦官は争っていたのだろう…?
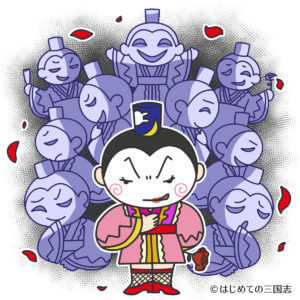
『三国志』を読んでいるとふとよぎるこの疑問。『三国志』の物語は、彼らの熾烈な争いによる漢王朝の弱体化により幕を開けます。でも、争っていた原因については特に言及されません。それは、当時の人たちにとって、外戚と宦官が争う関係にあることは当たり前のことだったから。しかし、現代の私たちにはよくわかりませんよね。今回は、外戚と宦官がなぜ争っていたのか、争いの原因は何だったのかを解説していきたいと思います。
外戚とは?
そもそも、外戚とは何なのか。外の親戚と書くこの外戚は、皇帝に嫁いできた女性の親族のことを指します。特に皇帝の寵愛を受けていた妃の親族はそれを鼻にかけて大威張り。でも、もっと威張れるのは次期皇帝候補となる男児を授かった妃の親族。たとえ正室の妃でも男児を授かることができなければ、肩身の狭い思いをしたことでしょう。
次期皇帝候補の男児が皇帝に選ばれたら、もう外戚たちの喜びようは半端ではなかったでしょう。帝の親族として大手を振って宮中を闊歩できますからね。政治にも口出しできるので、自分たちの都合のいい決まり事も作り放題。貴族たちは娘が生まれればこぞって後宮に入れようと争っていました。
宦官とは?
では、外戚と対立した宦官は何者なのか。彼らは、皇帝や皇帝の妃たちのお世話をしていた役人です。元々は宮刑に処せられて去勢されたり、捕虜となってしまった者が去勢されたりして任用されていました。去勢しているため、妃たちと間違いを犯すこともないということで、後宮の世話係に最適の存在だったようですね。
しかし、皇帝や妃たちのそばにいることから、中央の政治に口出しがしやすいということで権力を誇るようになってきた宦官。これを見て、自ら去勢して宦官を志願する者も現れるようになったのだそうです。
当時の価値観で両者を見比べると…?
宦官や外戚が火花を散らしていた後漢時代は、儒教の最盛期とも言える時代でした。前漢時代に武帝が董仲舒の進言を受けて五経博士の職を設置。儒教が漢王朝の国教になりました。以後、人々は儒教の勉強に励むようになったのです。
この儒教の教えの中に「孝」というものがあります。簡単に言ってしまえば、子は親を敬いなさいということですね。儒教の経典として『孝経』が著されていることからも、儒教の中で「孝」がどれほど大切なものとされているかがうかがえますね。そのため、皇帝の母は最も偉いはずの皇帝に敬われる存在として権勢をふるうことができました。
この皇帝の母の親族も続柄上、皇帝の「孝」を受ける立場ですから、その力を拡大していくことができたのです。「孝」の教えを最大限自分たちに有利に使っていたのが外戚という存在でした。一方、宦官は「孝」の教えの対極に位置するとも言える存在。儒教では、子孫を残さないのが最大の親不孝とされています。去勢されて自分の子を成すことができない宦官は、儒教が国教とされている漢王朝ではさぞ生きにくかったことでしょう。
それでも、皇帝や妃たちの最も近くにいることができたので、中央を操ることは朝飯前でした。「孝」の教えで最も蔑まれる存在である宦官は、「孝」の教えで最も尊重される存在である外戚を妬ましく思ったでしょう。しかし、妃となった娘を通してでしか中央に口出しできない外戚も、直接皇帝や妃たちに働きかけられる宦官を妬ましいと感じていたに違いありません。儒教的価値観が支配する世の中で、両者の対立は避けられなかったのですね。
儒教への反乱!?党錮の禁
宦官と外戚の対立は、長い漢の歴史の中で幾度となく繰り返されます。外戚であった王莽が漢王朝の帝位を奪って新を建国してからは、宦官と外戚の対立はますます激しくなっていったようです。後漢時代には幼い帝をいかに操るか、そればかり考えていた両者でしたが、和帝が外戚の口出しを煩わしく思い、その排除に宦官を使ってからは宦官勢力が優勢になりました。
しかし、宦官が帝を操るようになってからは汚職が横行。これに憤った儒学を信奉する豪族たちが清流派を名乗り、宦官を濁流派と罵り猛烈に批判しました。元々自分たちを出来損ない扱いする儒教が気に入らなかった宦官たちは、清流派と称する者たちを次々に誅殺。これが焚書坑儒に次ぐ儒者弾圧として有名な党錮の禁です。
その後黄巾の乱が起こり、ようやく終結したと思ったら宦官と外戚・何進との間で権力争いが勃発。宦官たちは何進の計略を見破り、返り討ちにしたものの、何進を殺されたことに憤った袁術・袁紹軍に皆殺しの憂き目に遭ってしまったのでした。
▼こちらもどうぞ
【三国志の原点】董卓を超えた暴虐者・梁冀と宦官の争いが後漢末の群雄割拠の原因だった?










