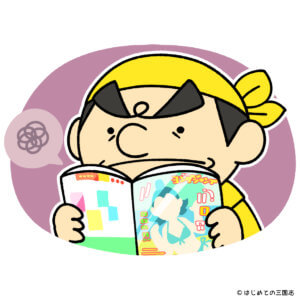30年くらい前までの日本は1億総中流社会と呼ばれる経済格差が小さい社会でした。また、格差の小ささは出身による差別というものを取り除き、日本においては、○○県出身者が就けない職業というものはありません。
どうして、日本においては歴史上格差が小さいのか?
今回は「土地と財産で読み解く日本史」を参考に、格差の小さかった日本の歴史について解説します。
この記事の目次
格差が小さいのは土地と財産を再分配していたから
日本において、経済格差の小さい平等社会が実現した理由は、歴史上何度も土地と財産を一手に握っていた権力者が倒され、彼らが抱えていた土地と財産が国民に再分配されたからです。
逆に言うと、世界史では一握りの特権階級が土地と財産を独占して国力が弱体化し天変地異や異民族の侵入により国が滅亡するという事が多くありました。
一握りの権力者に、土地と財産が独占されると99%を占める国民が活力を失い、国に従うのがバカらしくなり、暴動を起こしたり逃げたりして、やがて滅亡するのです。では、滅亡を回避した日本の土地と財産の再分配の歴史を見てみましょう。
民の救済としての大化の改新
日本における最初の土地と財産の再分配は大化の改新で行われました。大化の改新以前の大和朝廷は、各地の豪族の調整役という立場であり突出した力を持っていませんでした。
しかし、日本が朝鮮半島に持っていた植民地、任那や友好国である百済が大陸に成立した唐王朝や、新羅の朝鮮半島への侵攻により滅亡する事態に成ると、これまでのような調整役の朝廷ではなく、全ての豪族を支配下に置き、日本中の土地と財産を朝廷に集め強力な中央集権国家を樹立する必要が出てきました。
この朝廷にとって、もっとも邪魔だったのが物部氏を倒して最強になった蘇我氏であり、蘇我氏を滅ぼして、大和朝廷が全国の豪族の頂点に立ったのが大化の改新でした。
こうして、豪族から公地公民制で私有民と土地を取り上げ、さらに班田収授法で国民に土地を分け与え、収穫の3%という低率の税を取り、それまで豪族に搾取されていた人民から広く薄く租税を取る事で人民の暮らし向きを相対的に改善したのです。
公地公民が崩壊し荘園が広がる
一度は公地公民制と班田収授法で中央集権制を確立した大和朝廷ですが、100年程が経過すると、天然痘のような伝染病や、土地が私有できない事による耕地面積の停滞という社会問題が発生しました。
そこで、朝廷は三世一身の法、さらに墾田永年私財法を発布し開墾地の私有を認めたので、土地公有の原則が崩壊、開墾地面積でも寺社に広大な面積保有が認められたので、寺社は大土地所有者になり、各地に寺社荘園が急速に広がっていきます。
大和朝廷は疫病、天変地異、蝦夷討伐等で出費が増大、各地に国司を派遣しコストを掛けて行っていた口分田の再配分も出来なくなり、土地の把握も怪しくなって国有地まで、私有地として荘園に飲み込まれる事態が発生。
朝廷も、荘園整理令などで、不当に荘園に取り込まれた口分田を取り戻したりしていましたが、荘園の増殖は止める事が出来ず、朝廷は弱体化、畿内にしか支配力が及ばなくなり、地方には自警団としての武士が発生し、やがて、貴族に取って代わっていくのです。
複雑な税体系に苦しむ荘園農民
荘園が誕生した後、院政期から保元、平治の乱を経て、貴族が権力を失い鎌倉幕府が成立すると、征夷大将軍、源頼朝は全国の荘園に守護と地頭を派遣する事を後白河法皇に認めさせ、荘官と折半で年貢を取って御家人に与えるようになりました。
その後、鎌倉幕府が倒れ、室町幕府が開かれると軍事を司る守護に半済令が認められ、荘園から年貢の半分を徴収できる権限が与えられます。さらに「段銭」という税金を軍事費として荘園に課す権限まで守護は持つようになりました。守護はこうして、任地を経済的に支配する守護大名への道を歩み始めるのです。
荘園で働く人民は、荘官、地頭、守護、寺社勢力、加子地名主のような新興農民地主に何重にも税を取られ苦しい生活を強いられるようになっていきました。
戦国時代になると、守護大名や国人領主から室町幕府の影響力を一切排除して、領地を排他的に支配する戦国大名が誕生していきます。しかし、彼らは荘園の強大な中間搾取勢力である寺社や国人勢力を統治には邪魔だと思っても、紛争を恐れて排除する事が出来ず、結果、荘園の中間搾取はそのまま残されました。
中間搾取を撤廃した織田信長
この状況を根本から覆したのが戦国の風雲児織田信長でした。信長は中間搾取の最大勢力である比叡山延暦寺を徹底して叩き潰すなどして中世の既得権益を認めず、自国領において
「農民には原則として年貢以外に重い税を課してはならない」と触れを出しました。
信長が領地で定めた年貢は三公七民とも言われ、通常五公五民で合戦では臨時税も課された庶民に取っては、かなり低率の税金でした。こうして浮いた銭を庶民は遊興に使い消費に回したので織田領内では、経済が急速に発展していったのです。
900年近くも命脈を保った荘園ですが、戦国大名の実力介入で荘園領主の権利が浸食され弱体化、豊臣秀吉の太閤検地で土地1筆に所有者1人の原則が出来ると少なくとも表面上は消滅しました。
徳川250年の泰平を支えた領地の力
織田信長は部下に土地を分け与える封建制に限界を感じ、中央集権の公地公民制に戻そうとしていましたが、強固な封建領主である明智光秀の謀反により本能寺で倒れました。
明智光秀を討って信長の後継者になった羽柴秀吉ですが、低い身分から成りあがった出自の為に、公地公民制の構想を持っていたものの、部下に多くの土地を恩賞に与えて、忠誠を繋ぎとめるしかなく、直轄領は徳川家康よりも小さいものでした。
やがて、秀吉が没すると日本一の土地持ち大名、徳川家康が台頭し、関ケ原の戦いで石田三成を破り、西暦1603年江戸に幕府を開き、さらに大坂の陣で豊臣家を滅ぼします。
信長や秀吉と違い、公地公民制は採用しなかった家康ですが、関ケ原の合戦で西軍についた大名の土地を大量に没収しており、将軍家と徳川一門の土地を合わせると支配領域は800万石、日本の全耕作地の25%を抑えていました。
徳川幕府は圧倒的な石高と国内の主要な港と金銀、それに貨幣鋳造権を一手に握る事で、諸大名を完全に支配下に置き、鎌倉幕府や室町幕府とは比較にならない強大な政権基盤を整備し、日本は250年の空前の泰平と安定した政治を手に入れます。
土地の一極集中が起きなかった江戸時代
世界史を見ると、土地と富の一極集中が起きて社会が不安定化し、やがて旧権力を倒した勢力により、土地と富が再分配されるも、しばらくすると貧富の差が開き、土地の兼併と富の収奪が起きて、土地と富の一極集中が生まれて社会不安が増大するというサイクルを繰り返します。
ところが、日本では江戸時代末期でも小作農は30%程度で土地の一極集中は起きていません。
この理由は、農村においては、定期的に農地を振り替える割地と言うやり方で、絶えず各農家の収穫量に不公平が出ないように気を配り、また、やむを得ない理由で土地を手放しても、借りた元本さえ支払えば、何年経過しても土地は持ち主に戻るというシステムを採用していたからです。
また江戸時代の年貢は村請で、村全体で納税が割り当てられていたので、一軒農民が減ると他の農民の年貢が重くなるので、互助の精神が生まれ助け合いました。
それに江戸時代の年貢は当初の四公六民から、インフラ整備完了により三公七民になった後、再び計測し直される事がなく、耕作地が増える事で実質上の減税になっています。
もちろん、相対的に年貢が軽い幕府の天領と財政難に喘いだ諸藩では年貢や農民の負担は違いますが、人口が3000万人の時代に、年間400万人がお伊勢参りに出かけ「泥落とし」と呼ばれる農閑期の農民の慰安旅行が普通に行われていた事実を見ると、一般の農民には衣食住以外で使える、ある程度の可処分所得がある事が窺えます。
年貢負担の軽さによる可処分所得があればこそ、急な出費にもある程度対応でき、土地を売る最終手段に出なくて済んだし、また土地も元本さえ返せば戻ってくる、このような制度があればこそ小作農は30%という低い値に留まったのでしょう。
幕府による豪商取り潰しと徳政令
江戸時代には、商業は比較的自由であり、経済も発展して豪商も誕生しましたが、それにより大商人に富の一極集中が起きたという事はありませんでした。
その大きな理由は、幕府により私有財産が制限され、あまりに羽目を外した贅沢をすると、突然幕府に家が取り潰され財産を没収される事があったからです。
それに豪商には、富める者として社会的な責任が課され、防風林の植林や、堤防修理、架橋、大飢饉では義援金を供出させられるなど、決して安穏と利潤だけを追求していればいい存在ではありませんでした。
また、幕府は江戸中期から困窮しだした武士についても、享保の改革、寛政の改革、天保の改革で共通して徳政令を出し、武士の借財を棒引きにしていたのです。これは50年周期で行われ、武士は父の借金は背負っても祖父の借金は背負わないと言われました。
もちろん、一方的に損をする札差と呼ばれる貸金業者には、特別融資をするなどして幕府は経営を援助し、金融不安が起きないように配慮していました。だからこそ、金貸しと武士は持ちつ持たれつで、極端な貸しはがしなどは起きなかったのです。江戸幕府の強権が、財産と土地の一極集中を阻止し、富が再分配されるように機能していたんですね。
地租改正という農地解放
強力な権力基盤を誇り、250年繁栄した江戸幕府でしたが、18世紀末のフランス革命以来、欧州で次々と誕生した中央集権化した国民国家には太刀打ちできませんでした。
幕府を倒した薩摩・長州が母体の明治政府は封建制を放棄し、古代のように天皇を頂点においた中央集権制を施行し、富国強兵を実現しようと、版籍奉還、さらに廃藩置県を断行し300を数えた諸藩から土地と人民を中央政府に返還させたのです。
こうして封建体制を終わらせた上で明治政府は、土地をそのまま所有者である農民の物として与え、年貢ではなく土地の価格に3%の税を掛ける地租改正を行いました。つまり税金を物納ではなく金納にし、政府の財源を安定させようとしたのです。
この地租改正、教科書的には評判が悪く徳川時代よりも年貢が重くなったと不満を持った農民が、頻繁に一揆を起こしたとされますが、一揆が多く起きたのは年貢が安かった幕府天領の農民がメインでした。
明治9年米価の下落で、農民の収入が相対的に減少、3%の地租が重くなったので、三重、茨木、和歌山で一揆が頻発、これに不平士族の反乱と自由民権運動が重なり窮地に陥った明治政府は、地租を2.5%に引き下げ、以後は維持します。これは江戸時代の年貢に比較すると20%の減税でした。
江戸時代、土地は原則売買出来ず、植えられる作物もお上により決められていましたが、土地の私有が認められた事で、それらの縛りも撤廃され、農民は自分の土地を自由に使う事が出来るようになります。
地租改正が農民に取って決して悪くなかった証拠として、明治6年(1873年)と明治45年では米の収穫量が10アール当たり、24021石から50222石と2倍に増えている事でも裏付けられるのです。
地租改正は、戦後の農地解放とは比較にならない富の再分配でした。
武士の秩禄消滅と豪商の没落で明治維新は達成された
明治維新達成における最大の障害は、武家に先祖代々支払われていた固定給である秩禄と、経済的に困窮していた300諸藩が大坂や江戸や京都の豪商に負っていた莫大な借金でした。特に、武士の秩禄は国家予算の3割にもなり放置しておいては富国強兵など不可能です。
そこで明治政府は、300諸藩が負っていた債務を廃藩置県を契機に政府が肩代わりした上で債務をほとんど踏み倒し、武士の秩禄も、大幅減給した上に数ヵ年分を公債で支払うという形で打ち切りました。
つまり、武士と豪商に犠牲を強いる事で明治政府は債務整理し維新は成就したのです。特に武士の俸禄を切り捨てた事は俸禄で生活していた武士の反発を呼び、多くの不平士族の反乱に影響しましたが、明治政府は断行しました。
また「半世物語」によると江戸時代の大坂の豪商34家の中で維新期に23家が破産して家が絶え、明治以降も以前の勢力を維持できたのは9家に過ぎなかったようです。
借金棒引きも秩禄の廃止も、その分のお金を社会に還元したも同様です。明治維新は大きな犠牲付きの富の再分配だったという側面も忘れてはいけないでしょう。
日本史ライターkawausoの独り言
このように、日本では、豪族の私有民を解放し、人民に土地を与えた大化の改新、戦国末期の荘園の消滅による中間搾取の撤廃。
江戸時代の年貢負担の軽さや、三大改革期の徳政令の発布による武士階級の救済、そして地租改正による自作農の増加と武士の秩禄廃止や豪商が大名に貸していた借金の棒引きという、土地と財産の再分配が定期的に行われた事が分かります。
昔の日本の政治家は、放置すれば富も土地も一極集中し99%の国民が貧しくなる事を知っていて、度々既得権益に介入する事で再分配を繰り返し、それが経済格差が小さく差別が小さい日本社会を産み出したのです。
参考:土地と財産で読み解く日本史 大村大次郎 PHP研究所
関連記事:どうして戦国時代は人気があるの?大河ドラマでも視聴率が高い理由
関連記事:【麒麟がくる】戦国時代の関所は無益な銭取り装置だった