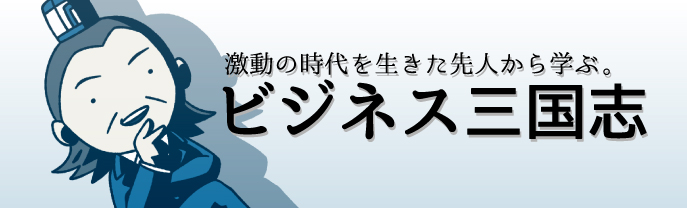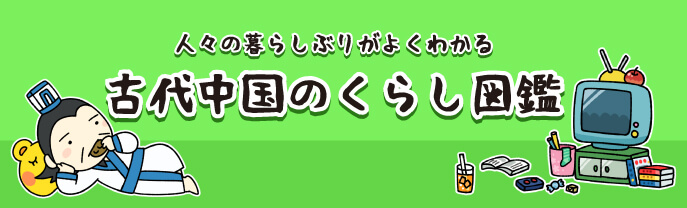通信機器が発達し、電話やメールでのやりとりが当たり前になっている昨今。仕事で手紙のやりとりをしているという人はいても、手紙で友人とやりとりをしているという人はなかなかいないのではないでしょうか?
一昔前までは主な通信手段として手紙は人々にとって身近なものでしたし、遠い昔から手紙でのやりとりは重要な通信手段として皇帝から庶民に至るまで幅広く用いられてきたものでした。では、いつから郵便制度というものは出来上がっていたのでしょうか?
実は、吾らが愛する『三国志』の時代には既に現代の郵便制度に劣らないシステムが構築されていたのだとか。今回は三国時代を中心に中国の郵便制度についてご紹介したいと思います。
郵便制度は秦代には整えられていた
郵便制度というとなんとなく近代的な響きがありますよね。
しかし、郵便制度というものは秦が中華統一を果たした後に生み出されたものでありかなり長い歴史を持つもののようです。秦の都・咸陽を中心に全国に幹線道路が延び、それらが手紙を運ぶための道として用いられました。幹線道路の道幅はなんと約80m!かなり広い道路ですね。
その道路の両脇には10m間隔で木が植えられていて、12kmおきに「駅」、4kmおきに「亭」、2㎞おきに「郵」という道の駅のようなホテルのような施設が置かれていたそうです。ただし、これらの施設を利用できるのは公人だけであり、庶民は利用できなかった模様。そのため、庶民が手紙をやりとりする際には、手紙を託された人が民宿に泊まって郵便物を運んでいたみたいですね。ただ、漢代になると庶民が亭を利用することも許されていたようです。こういった秦の制度は漢の御代になっても受け継がれ、厩律としてますます整備されていきました。
普通郵便から速達まで
庶民が手紙のやりとりをする際には託された1人の人が最後まで責任を持って手紙を相手に送り届けていたようですが、公人の手紙のやりとりは複数人の郵卒や信吏という役人たちが協力して行っていたようです。郵便担当の役人たちは赤い布を頭と腕につけ、紅白の文書入れを背負うというかなり目立つ格好をさせられていました。
彼らは1kmごとに配置されており、バトンをつなぐように手紙の受け渡しをしていたそうです。この郵便スタイルが現代の駅伝競走の起源となったそうです。しかし、彼らが全力で走ったとしてもはるか遠くの地に手紙を運ぶには日数がかかりすぎてしまうでしょう。それがもしも急を要する内容だったら大変です。
実は、「速達」の制度もしっかり完備されていたので、特に大きな問題は無かったようです。その当時の速達とは馬です。馬に乗って一気に走り抜け、馬が疲れたら駅で新しい馬と役人とバトンタッチしていくというスタイルなので、頑張れば1日に500kmは進めたみたいですね。
激動の時代を生きた先人たちから学ぶ『ビジネス三国志』
曹丕は厩律を郵易令に改めた
後漢時代の末期にもなると政治の腐敗などによって駅や亭、郵といった施設は減らされてしまい、動乱が起こるとすっかり廃れてしまいました。しかし、漢中王となった劉備は動乱の中でもそれらの施設を復活させようと尽力したようですし、曹操や孫権も各々それぞれ拠点として地を中心に郵便制度を整えていたことでしょう。
ちなみに魏では曹丕が皇帝に即位した後漢代に敷かれた厩律を郵易令に改め、後漢末期に衰えてしまった郵便制度を再び整えています。戦が絶えない三国時代では情報の有無がその戦況を左右しますから、いち早く手紙が届くように郵便制度を回復させる必要があったのでしょうね。
三国志ライターchopsticksの独り言
古代より手紙のやりとりは盛んに行われていたようですが、いわゆる宅配便のように物を届けることも多々あったようです。数々のお届け物の中でも厄介だったのはおそらく果物などの食べ物。
早く運ばなければ腐ってしまいますし、甘い香りにつられた猛獣が現れる可能性も高まるということで役人たちにとって運びたくない荷物と思われていたことでしょう。しかし、そんな荷物でもしっかり運ぼうと懸命に走った役人たちがいたからこそ遠くに住む人同士がその交友関係を保ち続けることができたのでしょうね。
関連記事:董卓の墓は存在するの?三国志観光旅行
関連記事:東方明珠のへなちょこ洛陽旅行記 その1
■古代中国の暮らしぶりがよくわかる■