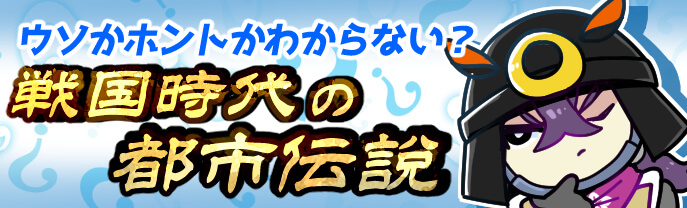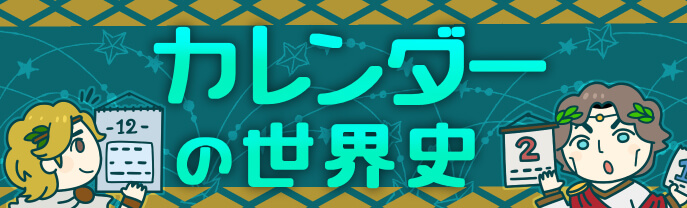ベンジャミン・フランクリンと言えば、アメリカの科学者であり実業家であり、アメリカ独立運動の指導者の1人として、建国の父達と讃えられる偉人です。彼は、ボストンの貧しい職人の子として出発し、苦学して印刷業を起こして成功した立志伝中の人物であり「時はカネなり」という名言でも知られます。
しかし、そんな偉人ベンジャミンには裏の顔がありました。彼は出版のノウハウを駆使し、悪質な手口でライバルを潰したペテン師だったのです。
この記事の目次
ボストンに生まれ印刷業に従事する
ベンジャミン・フランクリンは、西暦1706年に1月6日に、ジョサイア・フランクリンの15人目の子供として、ボストンのミルク・ストリートで誕生しました。1716年には、10歳で義務教育を終え、1718年「ニュー・イングランド・クーラント」紙を印刷出版していた兄ジェームズの徒弟となります。
当時、アメリカで興隆しつつあった印刷出版事業とベンジャミンの出会いです。頭のよいベンジャミンはすぐに印刷の仕事を覚え、記者や編集者としても頭角を現していきます。しかし、才能豊かなベンジャミンは、兄とよく衝突したようで、1722年にはニュー・イングランド・クーラントの執筆を止められました。
兄の新聞で未亡人になりすまし結婚の申し込みを受ける
ここでベンジャミンは、意図せずして最初のペテンの才能を発揮します。当時16歳、漲る執筆欲を強引に兄に抑え込まれたベンジャミンは、
「本名で書かなきゃいいんだよなぁ!」と開き直りサイレント・ドゥーグッドという中年の未亡人になりすまし、兄の雑誌ニュー・イングランド・クーラントに投稿を開始します。
ベンジャミンは、他人になりすます天才的な文才があり、兄は弟が未亡人になりすましているとは全く気づかず、14編もの投稿を掲載しました。機知に富み聡明なドゥーグッド夫人に、読者は惹きつけられ結婚の申し込みまで来たそうです。
しかし、いよいよ種切れになったベンジャミンは、ドゥーグッド夫人は自分だと打ち明けます。友人には褒められたものの兄には嫌われました。そして翌年には、ゴタゴタを起こして兄と袂を分かち、1730年には自分の新聞ペンシルヴァニア・ガゼットを創刊します。
貧しいリチャードの暦を発行する
敏腕編集者にして優秀な記者でもあったベンジャミンが興したペンシルヴァニア・ガゼット紙は、すぐに収益を上げていきました。しかし、印刷業で成功するには、新聞だけでは市場が小さく経営の多角化を考えないといけません。そこで、ベンジャミンが目をつけたのが暦を出版する事でした。
当時の暦は現在の新聞に替わる存在で、翌年に役立つ情報を予測し、日の出、日没、潮の干満、簡単な占星術、社説、天気予報、スポーツ、そして、農業に必要な情報が載っていました。
当時、アメリカで一番売れていた暦は、マサチューセッツのナサニエル・エイムズの暦で年間5万部の売上がありました。18世紀のアメリカ人の大半は農夫であり、新聞よりも暦が重要だったのです。
こうして、暦に目を付けたベンジャミンは、「貧しいリチャードの暦」という暦を出版します。どういうわけか、ベンジャミンはここでも匿名で、リチャード・ソーンダースという人物になりすまし、喰うや食わずの無想家が、口うるさい妻にせっつかれ暦を出版したという設定で書かれました。
ライバル、タイタン・リーズの死を予言する
この頃、アメリカの暦業界では、売上を競うライバル同士が「バカ」とか「間抜け」とか、紙面で相手を罵り合うという牧歌的な喧嘩が続いていました。
貧しいリチャードの暦の発行部数を伸ばしたいベンジャミンも、なんとかライバルを蹴落として注目を浴びようと、ある手段を考えます。それは、それまでの口汚い罵り合いが可愛く見えるような奇想天外なものでした。
それは、大御所の暦出版社、タイタン・リーズの死を宣告するものだったのです。ベンジャミンは占星術で、リーズが1733年10月17日の3時29分、太陽と火星が重なり合うまさしくその時に亡くなると、1732年の暦で予言しました。
通常、大御所出版社なら、新手の出版社の挑発には乗らないものです。有名人のTwitterに誹謗中傷をするフォロワーには反論よりブロックみたいなものですね。しかし、タイタン・リーズは生真面目で冗談の通じない人だったようで、ベンジャミンに対し、やってはいけない最悪の対応をしました。
翌年の1734年に出版した暦に、愚か者の「貧しいリチャードの暦」が、私が死ぬ等と言ういまわしい嘘をばら撒いたが、神の恩寵のお陰で私はこうして生きて1734年の日記を書く事が出来ている。このように反論してしまったのです。
SNSで言う所の燃料を投下してしまったリーズにベンジャミンは狂喜乱舞しました。大御所が喧嘩を買った、それだけで十分な話題になり貧しいリチャードの暦は売れるからです。
ところが、ベンジャミンはやはりペテンの名人でした。
大御所が死んだとおちょくり、発行部数が少し伸びた程度では終わらせるつもりはなかったのです・・
リーズは死んでニセモノが暦を書いていると煽る
ベンジャミンは、リーズの反論を受けて、1734年の暦で再反論を開始します。
「読者の皆さん、私はリーズ氏を名乗る亡霊から悪質な誹謗中傷を受けています。確かに、我が親愛なる友リーズ氏は死んだというのに、亡霊は未だに生きているふりをし私と私の予言に悪意を向けているのです」
ベンジャミンは、リーズの反論に驚きと困惑を見せ、現在の暦はリーズ氏の名を騙るニセモノ、リーズ氏の亡霊が書いたものと非難します。
さらに「こんな悪質ないたずらをして死者に対する配慮はないのですか?」と一体、どの顔下げていうのか?と思える良識ぶった対応をしました。
今なら、通信手段が発達していますからタイタン・リーズの生存確認は簡単ですが、18世紀前半では、大陸横断鉄道はおろか、電話さえありません。だから読者には、リーズの近所に住む人以外、どっちが本当の事を言っているか確認のしようがないのです。
生きていると言い張るリーズと、リーズのニセモノと言い張るベンジャミンの暦を通した論争は数年続きました。どうして、数年なのか?それは、1738年、タイタン・リーズは本当に死んだからです。
最強の荒しチャンプ、ベンジャミン
普通、論争していた相手が、不意に死んでしまえば流石にバツが悪い思いをするものです。ましてや、自分の暦を売らんとする為に、大御所の出版社に噛みついたベンジャミンなら、これにはさぞかし反省、やりすぎたと懺悔するか・・・と思いきや、彼は全く反省などしてはいませんでした。
西暦1739年、ベンジャミンは極めつけの一手を打ちます。
「あの世からタイタン・リーズの手紙が届いた」とうそぶき、タイタン・リーズの霊言という、どこかで聴いたようなタイトルの暦を発行したのです。
そして、貧しいリチャードが言った事は最初から最後まで正しく、本当のリーズ氏は、1733年にやはり死んでいて、その後の数年間はなりすましが書いたのだと念を押しました。
そう、このベンジャミン・フランクリンは相手の感情など何一つ考えず行動できる。絶対に絡んではいけない、ネット社会で言うヘビー級の荒しだったのです。しかも普通の荒らしは、誹謗中傷した相手を貶めるまでで終わりで、自分に経済的な利益は1銭もないものですが、荒らし王ベンジャミンは違いました。
この一連の論争で、貧しいリチャードの暦の評判はうなぎのぼりになり大ヒット、逆にリーズの暦は売上が激減し、10年後には廃刊になってしまったのです。
ま、仕方ないのです。これが市場と言うものですから、恐らく、読者は中傷合戦とはあまり関係なくリーズの暦よりも、ずっと歯切れがよく面白く魅力満載な貧しいリチャードの暦を価値が高いと感じて買ったというだけです。
論争で知名度が上がっても、貧しいリチャードの暦がつまらない内容なら、売上が伸びる事はありません。執筆者のリーズが死んで、以前からの読者が減ったという事もあったでしょう。でも、なんでしょうね、ムカムカする感情を抑えきれないんですけど・・
ゆるい都市伝説ライターkawausoの独り言
今回は、アメリカ建国の父の1人に数えられるベンジャミン・フランクリンの裏の顔を紹介しました。彼の悪事というかペテンは、こんなカワイイものではなく、実際に世界を巻き込んだような悪質なデマも飛ばしているのですが、その話は次の機会に致します。
ちなみに、日本語版のベンジャミン・フランクリンのWikipediaには、この話は一切載っていません。なんでなんでしょうね、、もしや、それは禁断の、、おっと、本日はこの辺で、、
参考:とてつもない嘘の世界史 トム・フィリップス
関連記事:【教科書に載らない歴史ミステリー】徐福は神武天皇になったってホント?
関連記事:戦国時代最大のミステリー・本能寺の変の謎に迫る!!