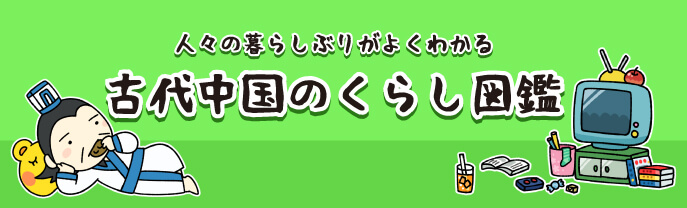三国志の世界は知将や猛将ばかりではありませんで、魏では曹操(そうそう)が
文化人だったので、様々な芸術家も雇われて、その腕を奮っておりました。
今回、紹介する梁鵠(りょうこく)もそんな文化人の一人で、彼の書は魏の宮殿の
全ての題字を飾っていたのです。
関連記事:曹操の求賢令が年々過激になっていて爆笑
この記事の目次
強い者には弱い、ヘタレな役人梁鵠
梁鵠は字を孟黄(もうこう)といい、涼州の安定烏氏の出身です。
幼い頃から書に興味を示して上達し、当時の書の第一人者である師宜官(しぎかん)に
弟子入りします。
その後、梁鵠は涼州刺史に転任しますが、支配下の武都郡の大守が宦官の仲常侍
(ちゅうじょうじ)の縁者で、その権勢をかさにきて賄賂を取り好き放題に
振る舞っていました。
たまりかねた部下の蘇正和(そせいわ)という人物が、これを弾劾しようとしますが、
仲常侍の報復を恐れた梁鵠は、蘇正和と仲が悪かった配下の蓋勲(がいくん)に
「蘇正和を口封じしてくれないか?」と頼んでいます。
蓋勲は、「そんな公私混同は出来ない」と突っぱねて蘇正和を庇いました。
このように梁鵠は行政官僚としては、不合格な弱虫君でした。
悪知恵で師匠を出し抜き、書の第一人者になる梁鵠
当時は道楽者の霊帝の時代でしたが、この霊帝は書を好んでいたので取り入りたい人々は
みんな書を練習して達人が多く出ましたが、師宜官は別格でどうしても勝てません。
師宜官も、それを理解していて筆法を真似されない為に、自分が木簡に書いた文字は
残さず、削り取ったり焼き捨てたりして研究させませんでした。
どうしても一番になりたい梁鵠は、一計を案じ、師匠である師宜官を
自宅に招いて宴会を催し沢山の木簡を用意して書を書かせてから、酒を大量に勧めて
ベロベロに酔わせ、その隙に師宜官の書いた木簡を一枚パクって熱心に研究します。
こうして、熱心な研究があって、梁鵠の書は師宜官を追い抜いて評判になり
撰部尚書(せんぶしょうしょ)に昇進する事が出来ます。
なかなか悪知恵のまわる所がある人ですね。
荊州で劉表に仕えていたが曹操に賞金を懸けられる
梁鵠が撰部尚書であった頃、曹操は仕官して洛陽の令になりたがっていました。
しかし、梁鵠はそれを叶えず洛陽の北部都尉に回しています。
その後、朝廷が乱れたので、梁鵠は荊州の劉表(りゅうひょう)を頼りますが、
そこへ覇者になった曹操がやってきて、梁鵠に懸賞金を懸けて探すように言いました。
「ひえええ!えらいこっちゃ、曹操は昔、私が洛陽の令にしなかった事を恨んで
殺すつもりなんだろうか」
ビビりの梁鵠は怯えますが、逃げ切れるわけがないと観念し、自分で自分を縛り
曹操の軍門に出頭します。
殺されるかと思いきや、曹操は梁鵠を仮司馬に任じて秘書として側におき、
書を書くように命じました。
曹操は、梁鵠の書を高く評価していて、それで懸賞金を懸けて探したのです。
曹操は宮殿の題字をすべて梁鵠に書かせるほど愛玩した
曹操は、梁鵠の書を幕内に吊り下げたり、壁に釘で打ちつけたりして、
これを愛玩した事が武帝紀に引かれた衛恒(えいかん)の「四体書勢」に出てきます。
曹操は、梁鵠の書をしげしげと眺めて、師宜官よりも優れていると言い、
後に魏の宮殿の題字は全て梁鵠に書かせる程になっています。
文武のどちらにも優れているわけでもなく、どっちかと言えば、
文官としてはヘタレの部類に入る梁鵠ですが、書の才能を持っていたので
曹操に重く用いられる事になったのです。
三国志ライターkawausoの独り言
三国志において、曹操が異彩を放つのは、その文学芸術への造詣の深さです。
建安文学の牽引者である曹操は、文学論については全くの万民平等を貫き
自分の文学論を押しつけず、優れていれば必ず賞賛しました。
このようなタイプはキングダムや水滸伝には見られない、三国志ならではの
特徴であると言えるでしょう。
関連記事:スーパーDr華佗が曹操に殺された意外な理由に涙・・
—古代中国の暮らしぶりがよくわかる—