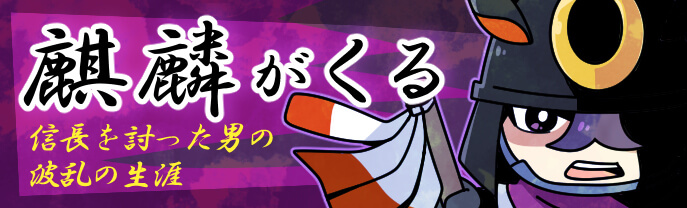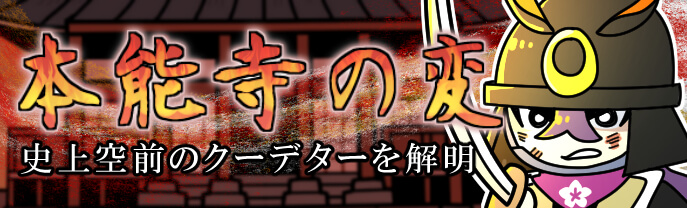明智光秀の盟友といえば細川藤孝が有名です。しかし、光秀にはもう一人家族ぐるみの付き合いをしていた吉田兼見という神主もいました。元々、兼見は藤孝の従兄弟である事から光秀と交友を結びますが、本能寺の変後、藤孝が光秀に同調しなかったのに対し、兼見は積極的に会うなど最後まで親しかったずっ友なのです。
従兄弟の藤孝の紹介で光秀と交友
吉田兼見は天文四年(1535年)京都吉田神社の神主、吉田兼右の次男として生まれます。本当は天正十四年(1586年)まで兼見は兼和という名前でしたが便宜上、この記事では有名な兼見で通します。元々、兼見の家は神主ではなく、兼見の祖父は学者の清原宣賢でした。しかし、吉田家当主の吉田兼満が突然出奔。吉田家は縁戚の宣賢の次男の兼右を養子とし実父の清原宣賢が後見して成長を待ちました。やがて兼右は元服し兼見が生まれたのです。
実家である清原家には兼右の姉か妹にあたる智慶院がいて彼女は三渕晴員に嫁ぎ、細川藤孝を産みました。このように吉田兼見と細川藤孝は従兄弟です。兼見がいつ光秀にあったか不明ですが、それは従兄弟の藤孝を介しての出会いとみるのが自然でしょう。
兼見と光秀の交友が始まる
吉田兼見が残した日記、兼見卿記によると、日記に光秀の名前が出てくるのは元亀元年(1570年)11月13日でこの日、光秀は吉田家に石風呂、いまでいうサウナを借りています。光秀は石風呂が気に入ったのか、この十日後にも入りに来ました。
以来、兼見卿記には、光秀とその家族がよく登場するようになります。光秀の妹か姉の御ツマキが吉田神社に祈願に来たり、光秀が美濃の親族の厄払いを兼見に依頼したり、坂本城が完成すると、その内部まで親しく案内されたり、
光秀が催す、茶会や連歌の会にも藤孝同様に、何度も参加しています。下手をすると最初に光秀を紹介してくれた藤孝との関係より濃いかも知れません。
光秀が兼見に便宜を図る
政敵やライバルには容赦がない光秀ですが、一方で身内と認めた人間には普通以上の気配りや愛情を示しました。例えば元亀三年3月3日、信長が上洛する時、光秀は事前に信長のスケジュールをつかみ、兼見に信長上洛を告げています。お陰で兼見は前もって準備を整えて信長を迎えて大いに面目を施し、黄金一枚を与えられています。
もうひとつ、吉田兼見は吉田山に吉田神社を持っていましたが、ここは禁裏や二条城に近く、比叡山や光秀の領地、坂本への中継地でした。この立地条件なら信長が接収して屋敷を築くのに最適であり、これを恐れた光秀は元亀四年7月。信長に吉田山を接収し屋敷を構えてはどうですかと勧めます。いやいや、勧めちゃダメじゃんと思うでしょう。
でも、これは逆なのです。信長は欲しいと思ったモノはどうしても手に入れたいと執着する人でした。だから、信長が吉田山に屋敷を築くと言わせる前に、光秀は自ら吉田山を信長に勧める必要がありました。
信長は多忙で自分で立地を見れないので、重臣の柴田勝家、羽柴秀吉、滝川一益、丹羽長秀、前波吉継という錚々たる面々を屋敷調査の為吉田山に向かわせます。織田家の重鎮を迎えた兼見は仰天しますが、五人は、あまり熱心に調べず
「ここは屋敷には不向きだから接収はない安心されよ」と言い去っていきました。
しかし、絶好の立地である吉田山が屋敷に適してないわけがありません。実は、この五人は光秀と折り合いが悪く、光秀が吉田山を信長に献上して増々、覚えめでたくなるのが嫌で結託して吉田山に×を出したようです。
光秀は、織田家中で孤立していたとルイス・フロイスは書いているので、光秀は最初から吉田山取得が織田家の重臣に潰される事を見越し、吉田山を守る為に敢えて信長に吉田山を取得する事を勧めたのだとkawauoは考えています。そうでないなら、その後も光秀と兼見の交友が途切れなく続いている辻褄が合わなくなるからです。
本能寺の変後光秀に会った兼見
天正十年6月2日、明智光秀は一万五千人の軍勢を率いて本能寺を襲撃。僅か100名の手勢しかいない信長は奮戦するも多勢に無勢、ついに抵抗を断念して屋敷に火を放ち自刃しました。
この時、光秀は縁戚関係にある細川藤孝はきっと自分に呼応すると信じていましたが、予想に反し、藤孝は信長の死を悼み、髷を切って動こうとしませんでした。一方で吉田兼見は積極的に動きます。
兼見は皇太子である誠仁親王の使者として、「今後の謀反の存分」を光秀に相談した事が兼見卿記の6月7日に出てくるようです。朝廷は信長死後に京都を抑えた光秀を天下人として認め、光秀と親しい兼見に今後の事を探らせようとしたのです。しかし、兼見と光秀が本能寺の変の後、どんな事を話し合ったか分かりません。
それは、元々兼見卿記に書いてあったのですが、光秀が三日天下に終わったので、焦った兼見が本能寺の変後の記述を破り捨ててしまったからです。
事実、兼見卿記は天正十年が正別の二冊あり、正本が1月から12月まであるのに対し、別本は、6月12日までの記録しかありません。これは兼見が都合の悪い部分を削除し、新しく正本に書きなおした事実を裏付けています。
戦国時代ライターkawausoの独り言
明智光秀と仲が良かったずっ友、吉田兼見は、その日記、兼見卿記を通して光秀の人物像の片鱗を見せてくれます。しかし、同時に近すぎたので本能寺の変を起こした光秀の動機という日本史最大のミステリーの答えを自ら破り捨てて闇に葬ってしまいました。もう少し、光秀と兼見に距離があれば、本能寺の変の動機は兼見卿記にそのまま残ったのかも知れません。
参考文献:明智光秀残虐と謀略
関連記事:どうして戦国武将は名刀を集めたの?
関連記事:【麒麟がくる】戦国時代の関所は無益な銭取り装置だった