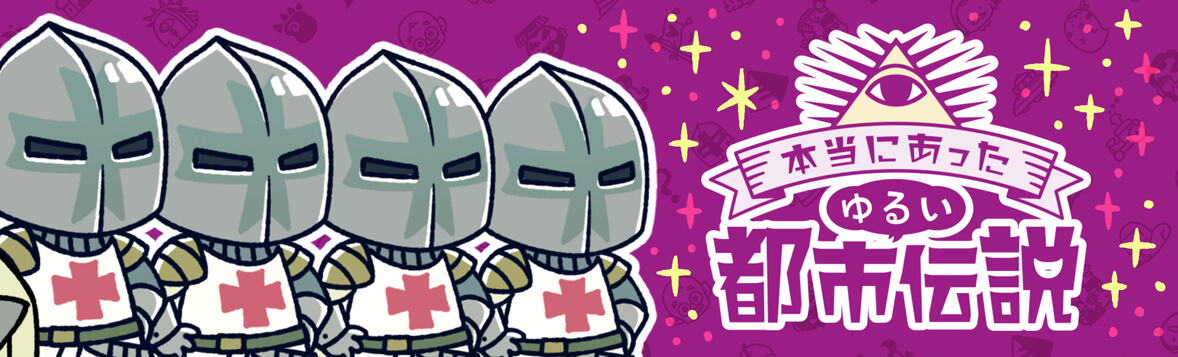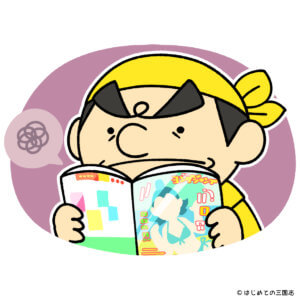
世界史の教科書で必ず習うフランス革命、教科書的には民主主義を広めたとされますが、実際のフランス革命は、血と粛清の連続、多くの有為な人材がギロチンの露と消えた、世にも恐ろしい政治的熱狂の時代でした。
そんなフランス革命の確かな遺産、それはフランス料理だったってご存知ですか?
この記事の目次
フランス料理はどうして美味しいのか?
さて、そもそもどうしてフランス料理が美味しいとされているのでしょうか?
それは、フランスがカトリック国である事に関係があります。
カトリックの教えでは、美味しいものへの愛や執念はキリスト教文明の善き作法、趣味の良さとして許容され、教会では食卓を社交や儀礼の場として重視していました。その為、美味しいものを求める罪悪感がなく、美食が発展していきます。同じく、カトリックが盛んなイタリアやスペインも料理が美味しい事で有名です。
逆に、プロテスタント教国では、料理や食べ物は飢えを鎮めるためのもので、余計な食欲をもたらすのは好ましくないとされ、料理の改良は進みませんでした。プロテスタントの国と言えば、イギリス、そしてアメリカですが、特にイギリスは料理がマズい事で有名ですし、アメリカはハンバーガーの国ですよね?
ルイ14世の時代にフランス料理は完成する
フランス料理は、元々イタリアから伝わったものですが、絶対王政下で洗練されていき、太陽王ルイ14世の時代には、料理ばかりではなく料理の彩どりや盛り付け、おしゃれな食器、テーブルアートに至るまで人々は凝るようになり、味覚だけでなく五感で料理を楽しむようになります。
しかし、この時代のフランス料理は、料理人が貴族に抱えられて腕を振るうだけで、庶民に開放されていたとは言えず、パリ市内全体でもレストランは50件に過ぎませんでした。
ところが、18世紀の末、フランス料理の運命を激変させる大事件が起きました。1789年7月14日のバスティーユ監獄の解放、つまりフランス革命の勃発です。
コンデ公の料理人がレストランを始める
バスティーユ監獄の解放から3日後、シャンティー城主のコンデ公ルイ・ジョゼフ5世は、ドイツに逃亡します。別に革命後に逃げた貴族はコンデ公だけではないのですが、彼の場合、少し事情が違いました。ルイ・ジョゼフ5世は美食家として有名でシャンティー城には大勢の料理人が働いていたのです。
彼ら料理人は、主が逃げた事で一夜にして失業、路頭に迷う事になってしまいました。
しかし、シャンティー城の厨房長をしていたロベールという人物が一念発起
「ピンチはチャンス!コンデ公じゃなくても美食家はいるハズ」とリシュリュー街104番地に自分のレストランを出して自活を開始します。
ロベールの目論見は大当たりします。
当時のフランスには中産階級の金持ちブルジョワジー達が勃興しており、舌の肥えた貴族の屋敷で腕を振るっていた料理人たちは、ブルジョワジーに絶賛され、たちまちのうちに大評判を取るようになり、失業問題は一気に解決しました。
フランス革命は動乱の時代で、一旗揚げようという大勢の男達が単身でパリに集まりましたが、彼らは料理してくれる家族を故郷に残しているので、食事に困りました。
そこで、営業時間内ならいつ入店してもよく、温かい料理を提供してくれるレストランは急速に普及、革命前に50件しかなかったレストランは、革命後1827年には3000件まで増加し、毎日6万人の市民が食事をするようになります。沢山のレストランが開かれた事で、フランスに外食文化が根付いたのです。
ギロチンとフランス料理
ナポレオンの時代のフランス料理は、ヴェリィで惜しみなく飾り付けされた膨大な数のスープと、魚および肉料理、そして何十ものサイドディッシュのメニューが売りでした。とにかく、ひたすら大量に飲んで食べるのが当時の食事のスタイルだったようです。
そして、そんなフランス料理とギロチンは切っても切れない関係でした。ナポレオンの帝政が始まる1804年までの25年間、フランスは政権が二転三転し、敗れた側はギロチンで容赦なく首を落とされていきます。
例えば、清廉な独裁者として有名な急進左派、ジャコバン党の首領ロベス・ピエールは少数与党のハンディを克服すべく、政敵を次々とギロチンに送り、4000名も殺害する恐怖政治を展開、そして、最期は彼もまた、ギロチンで首を落とされています。
さて、革命の動乱期、パリではいつもどこかで公開処刑があり、槍の穂先に突き刺した人間の生首や、首なしで馬に引きずられる犯罪者の死体が、そこら中を練り歩き、あろうことか市民の娯楽になっていました。
当時のレストランでは、今のようなメニュー表はなく、壁に張り紙をしてメニューを知らせていましたが、テュイルリー宮殿に近い、あるレストランでは、メニューの中に本日のギロチン犠牲者リストが掲載されていました。
そして、いつしかそのレストランは、ギロチン好き客のたまり場になり、ラ・ギョテーヌ(ギロチン亭)とあだ名されるようになるのです。
断頭台の処刑を見つつ、食べる人々
当時のギロチンは車輪がついていて土台ごと移動が可能でした。理由は、人を集めて広場で公開処刑をするためで、政敵を威嚇する残酷な政治ショーだったのです。そのため、広場に近く見晴らしがよい建物の2階ベランダ席は、概ねレストランであり、いよいよギロチン執行の時にはいつも大入り満員でした。
当時の紳士淑女は、大量に盛られた料理を食べながら、ギロチンの刃が落ちるのをハラハラドキドキで見物。
(ああ、あの気の毒な人と違い、私は生きていて本当によかった!)と生の充足感を見たし、
泣きわめき、あるいは堂々とギロチンに首を差し出す憐れな受刑者の断末魔を眼下に見下ろしつつ、異常な食欲で料理を平らげたのです。
平和に慣れた現代日本人には、異様な光景かも知れませんが、革命の嵐のフランスでは、人の不幸は蜜の味ならぬ、人の死は食欲を増進させる最高のスパイスであったのでした。
ゆるい都市伝説のまとめ
国王と貴族の所有物だったフランス料理は、革命が起きて貴族が国外に逃げ出し、料理人が失業しなければ、庶民にまで広がらなかった事でしょう。フランス革命が、民主主義を広めたかどうかは微妙ですが、フランス料理を庶民にまで広めたのは間違いない事実です。
そして、料理の食欲をそそるのは、ギロチンが産み出す人間の死という恐怖のスパイスでした。なんともはや、人間の食欲の業とは恐ろしいですね。
参考文献:民主主義という病い 小林よしのり ゴーマニズム宣言スペシャル
関連記事:ファティマの聖母とは?神の奇跡なんてほんとにあるの?
関連記事:ディビュークの箱とは?悪霊が封じ込められた戦慄の箱の実話