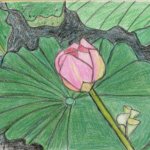こちらは3ページ目になります。1ページ目から読む場合は、以下の緑ボタンからお願いします。
この記事の目次
小牧・長久手の戦いの後世への影響は?
小牧長久手の攻勢への影響は、家康の力が温存されたことにつきます。秀吉は家康を武力で屈服できず、身内を人質に出すことでようやく家康が秀吉に従います。そのため家康は同盟していた関東の北条氏の仲介役をするなど、その影響力を残しました。
北条氏滅亡後、秀吉は家康の力を弱めようと、家康を関東に強制的に転封しますが、それで力が衰えることなく、晩年には五大老の筆頭として、幼い秀頼の面倒を依頼します。しかし秀吉の死後、家康は独自に動き出しました。再び戦乱の動きが起こります。
こうして東西に分かれて行われた関ケ原の合戦で勝利。徳川の時代を迎えることになりました。豊臣家は65万石の大名となり暫く生き残ります。ところが「自分の目の黒いうちに」と考えた家康が、言いがかりをつけて豊臣家を滅ぼそうとします。
それは秀頼が建てた京都の方広寺の鐘に銘打っていた「国家安康」「君臣豊楽」という文字に対して「豊臣を君主とし、家康を分断している」と言いがかりをつけます。そして豊臣家を滅ぼそうと軍勢を差し向け、大坂冬の陣と夏の陣の二回の戦いで、ついに宿敵だった豊臣家を滅ぼしました。
戦国時代ライターSoyokazeの独り言
信長、秀吉、家康という3人の英雄のうち、信長以外の両者が直接激突した戦い。戦そのものでは家康に有利でした。戦いは途中で終わりましたが、長期戦になったら家康が滅ぼされていた可能性がありました。しかし天正地震などがあり、秀吉が懐柔策を行うことで家康が屈服します。
これは武力制圧でなかったため、家康は力を温存したまま秀吉亡き後に、関ヶ原で勝利し天下を取りました。関ヶ原は天下分け目と言われていますが、秀吉と互角以上に戦った家康が何枚も上手だった理由がうなづけます。
関連記事:小牧長久手の戦いの勝敗はどうなった?漫画・センゴクから見る小牧長久手の戦い