
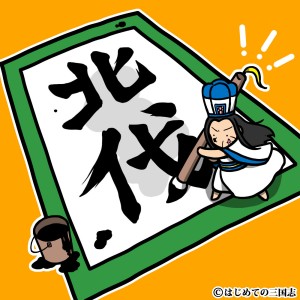
蜀(221年~263年)の建興9年(231年)に諸葛亮は魏(220年~265年)に対して北伐を起こしました。4度目の北伐でした。

以前から兵站(後方支援)が上手く行かずにすぐに撤退となっていました。だが、今回の諸葛亮は考えて出兵をしました。どこを考えたのでしょうか?
そこで今回は諸葛亮の第4次北伐について解説します。
関連記事:北伐で諸葛亮と敵対?昔のクラスメイト孟建と戦うことになった奇妙な関係性
続かない兵糧
諸葛亮は建興6年(228年)から魏の北伐を開始していました。1回目は街亭で馬謖が敗走したことで失敗、2回目は陳倉城の攻撃に手間取ってしまい撤退、3回目は長雨で動けなくなったので帰国になりました。
撤退理由の1つは敗北もありますが、最大の理由は兵站(後方支援)が全く続かないことでした。兵糧が続かなかったら、いくら勝利しても負けたことに変わりなしです。筆者もシュミレーションゲームの「三国志」や「信長の野望」をプレイした時に、手痛いほど味わいました。
木牛の発明
建興9年(231年)に諸葛亮は再び出兵します。ところが今度は、兵糧が続くように今までとは違うものを用意しました。それは「木牛」です。木牛というのは陳寿が執筆した正史『三国志』や『諸葛亮集』には登場するのですけど具体的な構造は現在も分かっていません。
北宋(960年~1127年)の高承は「手押し車のようなものじゃないですか?」と推測しています。蜀の桟道は険しいので、人が物をかついで渡るのは厳しかったし非常に手間のかかる作業です。木牛があれば蜀から最前線まで時間短縮で運べます。
諸葛亮も兵士たちも、ほっとしていたでしょう。
またもや兵糧不足
諸葛亮はこの第4次北伐で初めて司馬懿と戦います。小説『三国志演義』では最初から司馬懿と諸葛亮は戦っていますが、正史で2人が戦ったのはこれが初めてです。
蜀と魏は前哨戦の後に、お互いに主力戦を行いました。結果は蜀の大勝利に終わります。イケイケムードの蜀でしたが、ここでとんでもないアクシデントが発生。
蜀で兵糧を担当している李厳から「後方で兵糧が不足しているので、引きあげてください」と詔勅が届きます。諸葛亮たちは水を差された気分でしたが、兵糧が足りないし詔勅ならば仕方ありません。
司馬懿は蜀が急に帰国するので変だと思って張郃に追撃させますが、待ち伏せていた蜀の伏兵により張郃は討たれてしまいます。こうして追撃で被害が出ることもなく蜀の第4次北伐は終了しました。
李厳の虚偽申告
ところが諸葛亮が帰国すると李厳から、「兵糧は足りているのに、丞相(諸葛亮)はなんで帰国されたのですか?」と怪訝な表情をされます。諸葛亮からすれば狸か狐に化かされた気持ちです。
種を明かすと李厳は兵糧手配の仕事が上手くいかなかったので、ミスを諸葛亮の責任にしようと企んだのでした。李厳に対して不信感を抱いた諸葛亮は調査を開始。その結果、彼の虚偽申告が発覚。それどころか、劉禅にも虚偽報告をしていたことも分かりました。
虚偽申告に詔勅の偽装。普通ならば死罪ですけど李厳は劉備が死ぬ間際に諸葛亮と一緒に後を託された人物。勝手に死罪には出来ません。仕方なく庶民に落とすことで済ませました。だが、諸葛亮はこの一件で木牛だけでは兵站が続かないと悟ることになります。
三国志ライター 晃の独り言
以上が諸葛亮の第4次北伐と李厳の失脚に関しての解説でした。諸葛亮はこの件以降、北伐を中止。その後、建興12年(234年)に最後の北伐を行った時には戦場を開墾して兵糧をすぐに確保出来るようにしました。これで兵糧問題の解決に成功しました。
ところで李厳なのですが、この人は庶民に落とされても諸葛亮がまた自分を登用してくれると思って待っていたようです。現代に学ぶべきプラス思考かもしれません。さすがに諸葛亮が死んだと知ったら、ショックで寝込んで亡くなったようですけど。
死なずに生きて再雇用されたら面白かったかもしれません(笑)
※参考文献
・立間祥介『諸葛孔明―三国志の英雄たちー』(岩波新書 1990年)
・渡邉義浩『「三国志」の政治と思想 史実の英雄たち』(講談社選書メチエ 2012年)
※はじめての三国志では、コメント欄を解放しています。
諸葛亮が好き、または自分は李厳が大好きであるという人はコメントをどんどん送ってください。
関連記事:諸葛亮がもし延命していたら三国志はどうなる?第五次北伐後の孔明の戦略
関連記事:魏延がいれば陳倉の戦いは勝てた?それとも負けた?史実の北伐を解説
【北伐の真実に迫る】





















