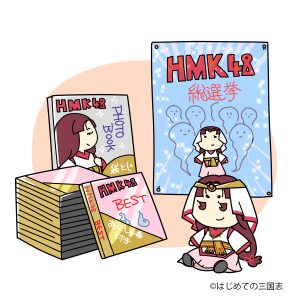今回は、邪馬台国の女王・卑弥呼(ひみこ)の使者として、二度に渡り、大陸の「魏」帝国の都まで赴き、二人の魏帝[二代目曹叡(そうえい)と三代目曹芳(そうほう)]に謁見している、難升米(なしめ)についての謎に迫り、書いていきたいと思います。よろしくお付き合いください。
関連記事:鬼道の使い手である卑弥呼の女王即位と三国志の関係性
1,邪馬台国の「内閣総理大臣」?
245年に邪馬台国の使者として、大陸の魏帝国の都まで出向き、三代魏帝の曹芳(そうほう)に謁見している上に、魏帝から、後世の日本で言うところの「錦の御旗」(にしきのみはた)的な、魏帝国の軍旗の「黄幢」(こうどう)を受け取っています。
これはまさに難升米(なしめ)が邪馬台国の代表といってよい待遇です。実質的な外交は難斗米(なしめ)に一任されていたと言ってよいでしょう。つまり、現在の「外務大臣」の立場だったとも言えますし、さらには、その権限はもっと強く「総理大臣」と言ってもよいかもしれません。それは、邪馬台国の実質的な最高権力者だったことを意味しているのではないでしょうか?また、邪馬台国代表ということは、この時代「倭国連合」の代表であったとも言えるでしょう。
2,邪馬台国軍の「征夷大将軍」?
さらには、その受け取った「黄幢」を邪馬台国代表として、受け取り、それを持って邪馬台国内まで帰ってきたということは、難斗米(なしめ)が、邪馬台国軍の総大将的な地位にいたとも考えられるでしょうか。「防衛大臣」や「軍総合司令官」的な役割も担っていたということでしょう。つまりは、後の日本の武家政権の棟梁「征夷大将軍」(せいいたいしょうぐん)と同じ役職と言っても良さそうです。
この戦乱の時代、武力を制する者が天下を制すると言っても良い時代だったでしょうから、いくら、女王・卑弥呼の「鬼道」(きどう)というカリスマ的能力が優れたとしても、戦乱の中で武力やその統率力が優れた者が上に立ち、国全体の政治にも影響を与えていく流れになるのも自然な流れでしょう。
3,卑弥呼を操ったか?
こうなってくると、難升米の存在は、もはや女王・卑弥呼の権力を越えていたと思えてきます。終には、卑弥呼を操り、傀儡政権と化していたのかという疑念がまとわりつきます。そこで、ここから少し想像して物語ってみます。
おそらく、女王・卑弥呼の即位当初は、「鬼道」というカリスマ性による求心力で、卑弥呼の権力は絶大だったでしょう。しかし、隣国の狗奴国(くなこく)との戦が長引き、立場の逆転に近い現象が起きます。苦戦続きの「対・狗奴国戦争」で、難斗米は陣頭指揮を取り、加えて、大陸の魏帝国の首都まで赴き、魏帝に会って激励を受けたぐらいですから、当時の邪馬台国内ではヒーロー扱いになっていたのでは?と考えられるでしょう。
いつしか、女王・卑弥呼は難斗米(なしめ)に頭が上がらなくなっていたかもしれません。言ってしまえば、平安時代末期以降に、力を持った武士集団の下克上が繰り返された事件の元祖にも見えてくるでしょうか?飼い犬に手を噛まれた状態だったか?とも考えられますね。
関連記事:松本清張も注目!邪馬台国(やまたいこく)はどこにあったの?
関連記事:衝撃の事実!卑弥呼はアイドル活動をしていた?通説・卑弥呼伝
4,そして、卑弥呼を暗殺したのか?
これは先回の記事の話題にも被りますが、「卑弥呼暗殺説」の疑いが浮上するという話です。前にも書いたように、卑弥呼が誰かに暗殺されたかもしれないという謎は残ったままです。暗殺・他殺説は消えたわけではないのです。つまり、卑弥呼は殺害され、難斗米が裏で関わっていたという可能性があるということです。
その可能性は否定できないのは確かです。ただ、直接関与した事実はなさそうです。と言いますのも、卑弥呼の死ぬ少し前、「対・狗奴国戦争」のため、「難斗米大将軍」は矢面に立たされていた訳ですから、卑弥呼と対面する機会はほとんどなかったでしょう。
あったとしても、直接手にかけるようなことをしては、未だカリスマ性の強い卑弥呼だったでしょうから、民の恨みを買い、難斗米自身の求心力が低下することは予想され、それは避けたかったでしょう。それでは、誰かを使って手にかけたか?という疑念が出てくるところです。しかし、その可能性は低いかもしれません。というのも、カリスマ性の強く、人心を掴んでいただろう卑弥呼が死んでしまうと、対狗奴国戦争中のため、士気の低下も案じられるところだったでしょうから、戦争の全指揮権を握っていた「難斗米大将軍」の立場上選べない選択肢だったでしょう。
すると、卑弥呼の死は、別の誰かによる殺害か、不慮の死か、老衰か?という謎がやはり残ったままとなります。少なくとも、難斗米が邪馬台国内、さらには倭国連合国の中で、女王・卑弥呼と勝るとも劣らずの権力を手に入れたのは確かなことでしょう。
関連記事:倭国 「魏志倭人伝」 から読み取る当時の日本、邪馬台国と卑弥呼を分かりやすく解説
関連記事:邪馬台国ってどんな国だったの?まさに神っていた邪馬台国
<おわりに>難斗米(なしめ)とは何者?
卑弥呼が謎の死を遂げた後、王位継承を巡り、邪馬台国を含めて倭国連合内が一時期乱れますが、新たな女王・台与(トヨ)が即位し、事なきを得て、倭国内は落ち着きます。そこに難斗米がどう関わっていたか、謎に包まれています。
次回は、卑弥呼死後の難升米の動きを探っていきます。それによって邪馬台国の行方と後の大和朝廷にどうつながるのか、闇に覆われた謎にも迫っていきたいと思います。何と、難斗米が大和朝廷成立にも大きく関わっていたという説もありますから、お楽しみに!
関連記事:曹真が余計な事をするから邪馬台国の場所が特定出来なくなった?