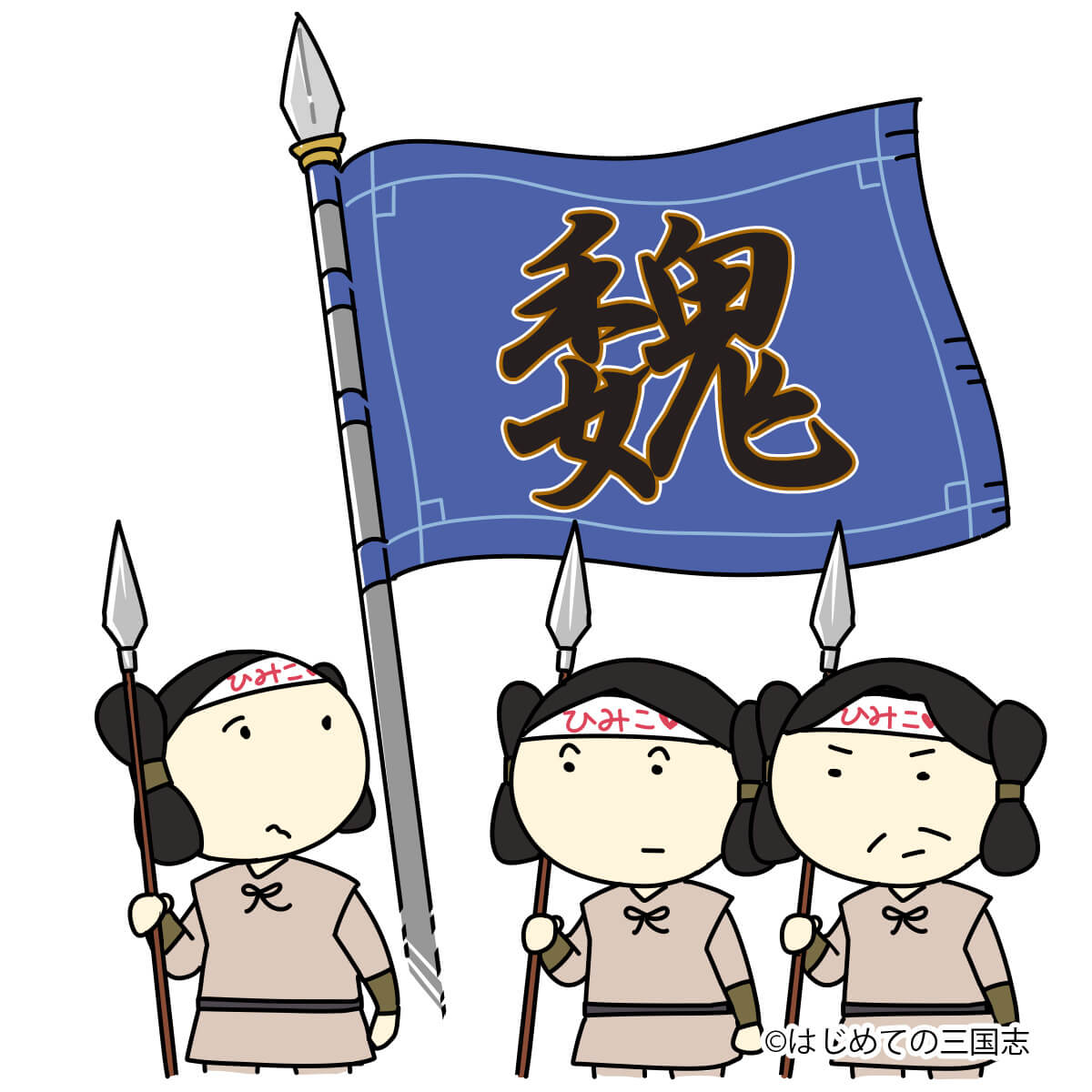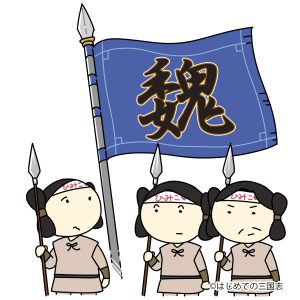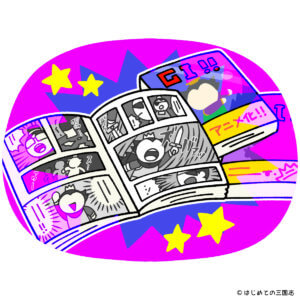本日は中国史と日本史、両方の古代のつながりについてお話ししたいと思います。「つながり」と一言で言うと様々なものがありますが、今回は親魏倭王と金印に付いて。親魏倭王の金印が発見された場所はどこなのか?その場所にはどのような歴史的な背景があるのか?
そして同時に、親魏倭王への金印はどのような意味を持っていたのか?その金印の授与にはどのような背景があったのか……色々と解説していきたいと思います。
この記事の目次
親魏倭王とは?卑弥呼と金印、詳しく解説!
親魏倭王は、「しんぎわおう」と読み、この親魏倭王というのは称号で、邪馬台国の女王・卑弥呼に西暦238年に与えられたものです。
与えたのはその名前からも分かるように魏の皇帝、二代目皇帝・曹叡。
ただ、卑弥呼に金印が与えられたのは西暦239年という説もあり、その場合の魏の皇帝は曹芳となります。ともあれ、魏の皇帝から卑弥呼に渡された金印のことを、その称号に準えて親魏倭王印、と呼ぶわけですね。
この背景として、237年まで倭国からの使者や貢物は公孫淵が遮り、自分のものとしてしまう、いわゆる横領が行われており、それが討伐されたことで魏と倭との交流が再開され、この際に皇帝が授けたのがこの称号と金印となるのです。
こちらもCHECK
-
-
3360名に聞きました!公孫淵はどこと組むのが一番いい?高句麗と邪馬台国も参戦?
続きを見る
親魏倭王の金印はどこかで見つかっているの?発見されている金印は?
さて、魏の皇帝が倭の女王卑弥呼に授けた称号と、その証である金印。この「与えた」こと自体は魏志倭人伝、そして日本書紀の神功皇后の巻に記録されています。ですが、その金印そのものは現代にいたるまで発見されていません。
このため、卑弥呼や邪馬台国の存在に関しては未だ議論がなされています。その一方で、別の金印が江戸時代に現在の福岡県、志賀島で発見されています。これは「漢委奴国王印」という漢王朝より授けられたもので、後漢書の記述と同一とすると光武帝が授けたものでは、と考えられているものですね。
こちらもCHECK
-
-
「卑弥呼」は実在したのか?「三国志」との関係は?
続きを見る
日本古代史を分かりやすく解説「邪馬台国入門」
「親魏倭王」とはどういう意味?政治的な背景も……
ここでちょっと親魏倭王、という称号の意味について。この称号は封号というもので、皇帝が朝貢を受ける代償として通交を許可するためのもの。号の意味だけを見るとするならば、倭の国の王様へ、魏の皇帝から親しみをこめて……という感じにでもなるでしょうか。と言っても、魏からすると倭は西方の国などに比べてそれほど重要な国でもなかったことは制書文面などからも読み取れます。
ですが倭、卑弥呼からするとこれはかなり重要な称号であったようです。その政治的な背景と、倭の国について次で述べていきましょう。
こちらもCHECK
-
-
魏に軍師を要請していた?卑弥呼が魏に使いを送る理由とは?
続きを見る
卑弥呼と倭国、そして魏の後ろ盾と当時の皇帝
元々、倭国は小さい国々の集まりでそれぞれを男王が治めていたのですが、2世紀に大規模な混乱期が訪れます。この際に混乱を納めるために卑弥呼という巫女を連合国家の王にして混乱を治め、邪馬台国と言う国が出来上がりました。ただこの卑弥呼、どんな人物でどういう血族で……ということがほぼ不明です。
このため、卑弥呼を王とするには後ろ盾が必要だったと思われます。そこで魏へ使者を出し、親魏倭王として封号されることで正当性を得ようとしたのではないのでしょうか。
因みに卑弥呼は247年に死去したとされていますが、卑弥呼が使者を送ったのが238年、この年代なら任命したのは曹叡です。
しかしこれは239年の誤記とされる説もあり、その場合ならば皇帝は曹芳となります。
またこれらの記述は中国の三国志、魏志倭人伝に記録されているものであることも大きなポイントとなります。
こちらもCHECK
-
-
邪馬台国の卑弥呼政権時代は倭国大乱は継続していた? 魏志倭人伝に秘められたプロパガンダー
続きを見る
三国志の魏志倭人伝とはどういう意味?
魏志とは、三国志の魏書の通称であり、その中にある倭人という記録のことを魏志倭人伝と言います。倭人とは倭国のことで、国との交流を経て中国から見た記録になります。ただ少し勘違いされやすいのですが、三国志に倭人について独立した列伝があるわけではありません。
三国志、魏書の第30巻に烏丸鮮卑東夷伝と言うものがあり、その中に倭人についての項目と記録がされている部分を指して、魏志倭人伝と呼ぶのです。ここに親魏倭王の号も出てきますよ。
こちらもCHECK
-
-
魏志倭人伝とは何?陳寿に感謝!三国志時代の日本がわかる
続きを見る
親魏倭王と漢委奴国王の違いは何?
さて、親魏倭王と漢委奴国王の違いに付いても触れていきましょう。まず漢委奴国王は前述したように漢王朝から授けられたもので、後漢書に記述があるものとされ、漢の国から倭の奴国の王に授けられたものであり、こちらは発見されている金印となります。
そして親魏倭王の方はそこから200年ほど経ち、魏の国から倭国の王として卑弥呼に授けられた金印とされています……が、こちらは三国志に記述されているのみで、実物は確認されていません。
ここで「倭国というけれど「委」と「倭」は違うのでは?」と思った方もいるでしょうか。「漢委奴国王」は「かんのわのなのこくおう」と読むとされていて、実は「委」を「わ」と読むのです。このため、「倭」と「委」は同じ意味であると言えます。恐らくは、金印とする際に文字を簡略化するために「漢委奴国王」として、別の文字を当てたのではないでしょうか。つまり両方とも、同じ倭国の王へ授けられたものと言えるでしょう。
こちらもCHECK
-
-
「漢委奴国王」と刻まれた金印ってどんなもの?教科書でもお馴染みの金印
続きを見る
卑弥呼が魏に使いを送った、もう一つの理由
最後に、卑弥呼が魏に使いを送った理由について、もう一つ挙げさせて頂きます。一つは後ろ盾、魏と言う大国から任命されている、という正当性を得るためと考えました。もう一つは「援護」です。卑弥呼が治めていた邪馬台国は、そこから南に(もしくは東に)あると言われる狗奴国という国と争いが起きていました。
狗奴国は男王・卑弥弓呼という人物が治めており、魏書東夷伝によると「もとより和せず」と、決して卑弥呼は相いれる気はなかった模様です。二つの国の戦いは魏に報告され、247年に張政が派遣され和議を結ぶように、と仲介がされています。
ただ、この頃に卑弥呼は死去、狗奴国は元より、卑弥弓呼もその後はどうなったのかは分かりません。卑弥呼は巫女であり、不思議な術を用いて占いが得意だったとも言われていますが……もしかしたらこの8年前に使者を出したのも、自分の死期を知っていたから?それとも……?何にせよまだまだ未知の部分が大きな邪馬台国とその女王。今後、何かしらの発見がされることを日々待っています。
こちらもCHECK
-
-
狗奴国とはどんな国?邪馬台国の卑弥呼に抵抗した国を分かりやすく解説
続きを見る
三国志ライター センのひとりごと
調べてみれば調べるほどに、未知数としか言いようがない邪馬台国と女王卑弥呼。またその周囲も謎が多く、日本であった出来事や人物でありながら不明な部分が大きい時代でもあります。だからこそ論争は日々絶え間なく、人々の考察や興味を湧き立てるのでしょうね。
ぜひこれからもこれらの出来事に光明が差すことを祈るばかりです。どぼーん。
参考:魏志倭人伝 魏書公孫淵伝
こちらもCHECK
-
-
邪馬台国ってどんな国だったの?まさに神っていた邪馬台国
続きを見る