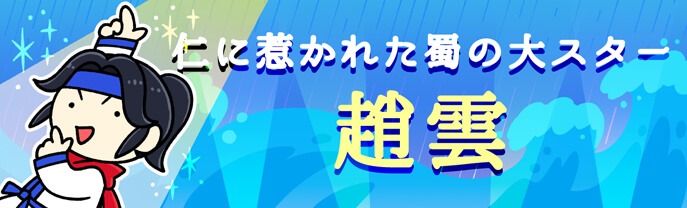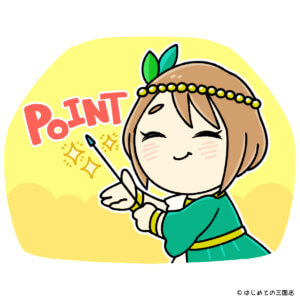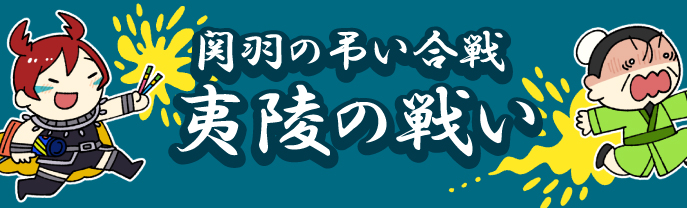皆様は、劉玄徳に対してどんなイメージがありますか?
さて、こんな質問をするとどうしても上がってきてしまう話題、それは「劉備は戦上手か否か」があります。逆を言うと「戦下手か否か」になりますが、それは一先ず置いておいて。
近年、この劉備は戦上手だった!いや、寧ろ逆だろう!という話が再熱している兆しを感じますね。そこで今回は、三国志をテーマとしたビッグネームゲームに最新作が出てきた衝撃も兼ねて、この劉備の戦に関しての手腕を考察してみたいと思います。……推しの登場はまだかな(ボソッ)
この記事の目次
劉備の戦上手に関する評価と、変わりつつある現代の見解
さて「劉備は戦上手か否か」についてはまずは一先ず置いておきますが、劉備というのは昔は「戦は苦手」というイメージが大きかったと思います。というのもやはり三国志演義のイメージが一般的に強すぎたという理由があるでしょう。
一例を挙げると三国志演義では「博望坡の戦い」の戦いで夏候惇、及び曹操陣営を苛烈に打ち破るのは諸葛亮の知略あってこそのもの、これは読者に諸葛亮の凄さを見せつけると同時に、それまで諸葛亮に懐疑的だった関羽や張飛から受け入れられていく、という重要な意味を含んだシーンとなります。
しかし、実際に勝利したのは劉備の手腕あってこそのもの。
ではどうしてエピソードに差があるのかというと、そもそも歴史的評価では劉備に「戦が強い」というイメージは不必要であり、三国志演義で劉備の最大の魅力は仁徳、そしてまだ弱い主人公が力強い仲間たちに支えられ強大な悪に立ち向かっていく……というドラマとロマンこそが必要であったと考えられます。
そうなった際に、劉備に戦の要素は寧ろ不要、劉備は徳を示す存在であり、その強さを示す役割は「劉備の仁徳に惹かれてやってきた仲間、及び部下」に求められる者であったのではないでしょうか。ですがそのフィルターが現代では薄れていき、寧ろ歴史書の記録に触れていくことにより「あれ……劉備割と勝ってるな……?」そんなイメージ出て来たのではないかと思います。
関連記事:劉備が大勝利した博望坡の戦いを語ろう
こちらもCHECK
-
-
もしも徐庶が三国一のサボタージュ名人だったら?博望坡の戦いの裏を勘ぐってみた!【三国志演義】
続きを見る
劉備の戦術的な才能を、その戦法から分析する
ここで劉備の戦術の才能一つ語らせて頂くために、二つの戦、まずは博望坡の戦いでの話をご紹介しましょう。
記録によるとこの戦いで劉備はまず自陣に火を放ち撤退したように見せかけ、それに釣られた夏候惇、及び于禁を伏兵によって打ち破りました。
この一件から「劉備はゲリラ戦が得意なのでは?」「もしかして少数の内は良かったけど、大軍を率いるのは苦手?」と言われますが、注目して欲しいのはその後、救援に李典が駆け付けると、劉備は素早く撤退しています。
同時に上げたいもう一つの戦いが、長坂の戦いです。
ここで曹操は劉備が江陵を占拠することを危惧し、強行軍にて劉備に追いつきます……すると劉備は妻子すら捨て、数十騎で逃走、これにより劉備は見事落ち延び、赤壁の戦いに繋がりますね。さて、戦法と言って良いのかは分かりませんが、劉備は逃げるのが非常に上手です。
しかも長坂のような劣勢から、博望坡での勝利ムード状態からでも、逃げ時を逃がさない人物です。この戦局を即座に見極める判断力、これは劉備の戦術的、そして戦略的な才覚であり、最大の戦法の一つと言って良いのではないでしょうか。因みに個人的には劉備の戦歴で、大軍を率いている定軍山のケースがあるので、決して大軍を率いるのが苦手という訳でもなかったのだろうと思っております。
関連記事:長坂の戦いの全容はあっさりめ?劉備と趙雲の逸話などはどこまで本当なの?
こちらもCHECK
-
-
長坂の戦いとはどんな戦いだったの?
続きを見る
戦上手の条件とは?戦と兵站の重要性
ちょっとここいらで「戦上手の条件」について考えてみましょう。
この戦上手の条件に付いて「戦上手は兵站上手」という有名な文句があります。
兵站とは前線への食糧や武器などの補給作業とそれらの維持、道の整備や兵員確保など、様々な準備や支援なども取り上げられますが、これらが上手な人ほど戦上手ということですね。
個人の観点ですがこれを実践した例として、豊臣秀吉(羽柴秀吉)とその配下が挙げられると考えています。
羽柴秀吉が中央から離れていたにも拘らず明智光秀を打ち取れた要因の一つに中国大返しがありますが、この際に秀吉は「山を歩いていた怪しい飛脚を捕らえたら密使だった」「その後、信長暗殺の情報が漏れないように街道の完全封鎖」をしたとされ、これは本拠地から離れながらも秀吉が補給作業、つまりそこまでの「道」をしっかりと抑えていた、つまりは兵站がしっかりされていた、という理由となると考えられます。
関連記事:地味だけど超大事!三国志の時代の食糧貯蔵庫とはどんなもの?
こちらもCHECK
-
-
なぜ蜀漢の北伐は兵站維持に失敗したのか?食料事情から原因を考察
続きを見る
諸葛亮との連携作業と、兵站の難しさ
この兵站の重要性を考えますと、劉備の兵站を支えていたのは後方支援担当、諸葛亮でした。更に言いますと、その後、諸葛亮の兵站を支えていたのは恐らく蔣琬ではないかと考えられます。
ここで重要なのが、兵站を維持するということは、国力という限界があるということです。弱くて貧乏では、戦線の維持というのは非常に困難、強くてお金持ちであれば、多少負けてもまた盛り返せますが……例えそうであっても、永遠ということはあり得ません。
そういう意味でも、内政の才能を評価される諸葛亮が軍事に動かねばならない状況というのは、非常に国として「ヤバい」状況だったのでしょう。つくづく、龐統や法正の早期退場が惜しまれますね、蜀は。
関連記事:蜀はなぜ北伐に乗り出したの?その目的は?
こちらもCHECK
-
-
北伐失敗ならいっそ呉を攻めるべき?孔明が「魏への北伐」ではなく「呉への東征」を行うと三国志はどうなる?
続きを見る
【北伐の真実に迫る】
曹操と劉備、彼らの戦略を考える上での根本的な違いはどこに
さて劉備が逃げ上手で撤退が上手である、ということは前述しましたが、曹操にその観点が欠けているとは思いません。
曹操も危機的状況を何度も家臣たちの働きで切り抜けていますし、夏侯淵や張遼に「指揮官の戦い方」について話している所を見ると、その重要さも理解していたことでしょう……まあ夏侯淵や張遼はあんまりこれを聞き入れていないようでしたが……コホン。
劉備が曹操に勝利した!と言える定軍山の戦いでも、「鶏肋」という言葉があるように、時として身を切ることの重要性も理解していたと思われます。
と、こう考えると劉備と曹操の戦略性は似ていたのではないか?
寧ろ根本が似ていたことを考えると、曹操が劉備を評価していたことの理由にもなります。では何が違うかというと……その国力、基盤の大きさの違いこそが二人を別けた重要なファクターであったと言えるのではないでしょうか。
その上で「王は一人でなくてはならない」……これを考えると、劉備が曹操から離れたのは、ある意味、曹操という人物がいる国では、自らが王になることはできないと理解していたから……と考えてみてはどうでしょうか。そういう野心のある劉備もいいと思います、ええ。
関連記事:「劉備、軍事が苦手説」を検証する!
こちらもCHECK
-
-
劉さんぽ!中国大陸を歩き続けた劉備の足取り
続きを見る
劉備の戦でのエピソードから読み取れるものとは
と、ここでとあるエピソードを思い出して頂きましょう。定軍山の戦いの最中、劉備に撤退の申し出をするも頭に血が上がってしまった劉備はこれを受け入れないだろうと誰も咎めない。
そこで法正は自ら劉備の前に出て、その身を庇いました。
これに劉備が驚いて矢を避けるように言うと「公が矢や石の飛び交う中におられるのにどうして私ごときが避けられましょう」と答え、やっと劉備は冷静になり後退しました。
後に、劉備は関羽の仇と怒りに打ち震え、夷陵の戦いに燃え上がります。まあ後々炎上するのはこの劉備の方なのは言うまでもないのですが……しかし、この法正とのエピソードで、劉備の致命的な欠点が見えてくるのです。
関連記事:劉備を唯一なだめられた、法正(ほうせい)ってどんな軍師?
こちらもCHECK
-
-
法正のすごさとは?諸葛亮が認めた驚きの真実
続きを見る
夷陵の戦いでの「もし」と、劉備の致命的な欠点
夷陵の戦いでは劉備はどんどんと進軍し、兵を進めていきます。これに危機感を感じた黄権が、「これ以上侵攻すると撤退が困難です、自分が指揮を執りますので後方に下がられますように」と進言しました。
しかし劉備はこれに止まらず、兵を進めていき……最終的に、白帝城まで退くことになります。これを合わせて考えると、劉備はどうにも頭に血が上ると冷静な判断ができない傾向が強いです。いえ、誰だってそうではあるのですが、それは、皇帝となっている人物の欠点としては致命的です。
また、法正の際にも誰もそのことを指摘できず、法正が諫めてやっと……と考えると、劉備は冷静さを欠くと、他の武将たちとの協力が疎かになる傾向が見られます。だからこその諸葛亮の「法正殿がいてくれたら」だったのではないでしょうか。ですがそれもまた、ある意味では劉備の魅力であったのかもしれません。
皇帝となって尚、冷静さを「欠くことができる存在」という人物は、当時としては非常に魅力的な存在であり、稀有であったのかもしれませんね。だからこそ劉備は、まるで戦が下手に見えるかのように、三国志演義では描かれたのかもしれません。
こちらもCHECK
-
-
劉備が慕われる理由とは?漢室復興の「徳」を解説
続きを見る
三国志ライター センのひとりごと
筆者の個人的意見で言わせて頂きますと、劉備は決して戦下手などではありません。寧ろ上手の部類に十分に入る人物でしょう。
魏の張コウの恐ろしさを十分に分かっている所を考えると、華々しい戦果を果たす者よりも、もしかして慎重派で冷静な人物を警戒しているようにも見えます。
そう考えると、劉備は自分の「冷静でなくなること」を欠点として理解した上で、それを諫められるような存在である法正を重用したのかもしれません。
しかしそう考えると……世の中、ままならないなぁ……と思う筆者でした。どぼん。
参考:蜀書先主伝 法正伝 魏書夏侯淵伝 常山紀談
関連記事:晩年の劉備は嘆くこともできなかった?現代にも通じる嘆きと髀肉の嘆
こちらもCHECK
-
-
劉備は曹操と天下を争う気はなかった?陳寿の人物評がなかなか面白い
続きを見る