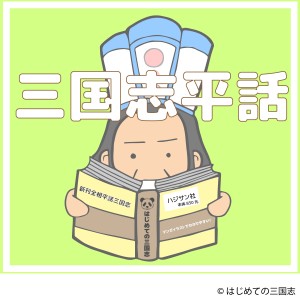皆さんは『三国志』の世界にどのようにして誘われたのでしょうか?
おそらくほとんどの人たちが『三国志演義』をベースとする作品から『三国志』の世界への扉を開けたのでしょう。『三国志』を好きになると、『三国志』のことをもっと知りたい!と思いますよね。そんなあなたは『三国志』には正史とされる陳寿の『三国志』と、それを元に作られた作者不明の『三国志演義』の2種類があることを知ります。ところが、さらに調べていくと、『三国志平話』というものの存在に行き当たるでしょう。『三国志演義』の原典とされるこの『三国志平話』という作品は、一体どのような物語なのでしょうか?
序盤からファンタジー全開!
『三国志平話』とは、元代に刊行された説話集『全相平話五種』の中に収録されている『新刊全相平話三国志』のことを指します。明代の爆発的小説ブームに先んじて生み出された作品のようですね。
平話とは歴史物語のこと。大衆向けの歴史物語として世に出されたこの『三国志平話』、とてもありがたいことに、なんと全てのページに挿絵があるのです。挿絵があれば、小さな子どもでも内容を理解できますし、その情景をまざまざと思い浮かべることもできそうですよね。ぜひ手に取って読んでみたいところ。ではさっそく読んでみよう。どれどれ…とページをめくってみると、…なんじゃこりゃ!?と驚かずにはいられません。おそらく何人かは自分が読んでいるその本の題を確認することになるでしょう。
天帝さまの言うとおり?
『三国志平話』の冒頭の舞台はなんと「あの世」。それも、裁判の真っ最中。裁判長は後漢・光武帝に仕えていた司馬仲相。原告は漢建国の立役者でありながら謀殺された韓信・彭越・英布の3人。そして、被告は彼らを死に追いやった漢の高祖・劉邦とその妻・呂后。錚々たる顔ぶれです。
原告3人は、被告の所業を挙げ連ね、その無念を訴えます。それに対し、そんな証拠はないだろうと開き直る被告側。しかし、そこに原告の言葉を裏付ける証言を持った蒯徹(通)が現れます。それを受けた司馬仲相は被告に有罪を言い渡し、来世でその報いを受けるように命じます。
裁判の結果を受けた天帝は、韓信を曹操に、彭越を劉備に、英布を孫権に、劉邦を献帝に、呂后を伏皇后に転生させたのでした。更に、蒯徹をしょかつりょう、司馬仲相を司馬懿に生まれ変わらせます。その行く末を知る天帝の思惑通りに事が運ぶのか、はたまた天帝の予想を裏切る展開が起こるのか…。
全体的にテンションが高い『三国志平話』
『三国志演義』には、R15指定を免れないのでは!?と思うほど血しぶき上がる描写があふれていますよね。何とも大袈裟な…と苦笑いしてしまうほど。しかし、『三国志平話』の描写はそれに輪をかけてバイオレンス。たとえば、劉備が黄巾の乱で功を挙げ、安熹の県長として赴任した際、『三国志演義』では押し掛けてきた督郵を張飛が縛り上げ、柳の枝で200発打って逃亡したと描かれているエピソード。
原典にあたる『三国志平話』では劉備に因縁をつけて罰しようとした督郵を裸にして柱に縛り付けて杖で100発打って殺害、その死体を6つに切り分け、その死体を外に晒し上げて逃亡するというさらに凄まじいエピソードだったのです…!
『三国志演義』の方でさえ「張飛やりすぎ…」という感じなのに…。元ネタを知った上で『三国志演義』のエピソードを読むと、穏やかになった表現に作者のあたたかい配慮が感じられますね。その他、『三国志平話』のバイオレンスエピソードは枚挙に暇がありません。このようなバイオレンスな世界観の中で最も輝いていたのは他でもない張飛。『三国志演義』では猪武者で足を引っ張ることが多いイメージの張飛も、『三国志平話』では主役級の活躍を見せています…。
逆に、冷静さが売りの関羽や諸葛亮の活躍は少なめ。『三国志平話』は大衆向けの物語でしたから、智謀だの計略だのせせこましいことよりも、大胆でテンションが高い方が受けがいいと考えられていたのでしょうね。それでも、『三国志演義』で見られる高徳の劉備VS奸雄・曹操の構図は『三国志平話』から変わらずに受け継がれていることがうかがえます。勧善懲悪物はいつの時代も、どの層の人にも支持されていたのですね。
荒唐無稽な世界観…だが、それがいい
『三国志平話』は、歴史物語と称されていながら、史実にそぐわないことが多く、その世界観もぶっ飛んでいたことから多くの知識人からはそれほど評価されていません。しかし、『三国志平話』が矛盾を抱える作品だったからこそ、『三国志演義』という作品が生み出されるに至ったと考えることもできるはずです。『三国志平話』の珍妙奇天烈な世界観は人々の想像力や創造力を駆り立ててくれるという点では評価に値するものだと考えてもいいのではないでしょうか。
※この記事は、はじめての三国志に投稿された記事を再構成したものです。
▼こちらもどうぞ