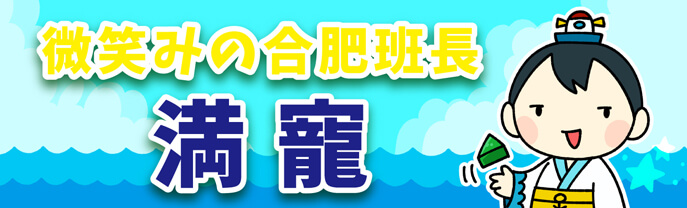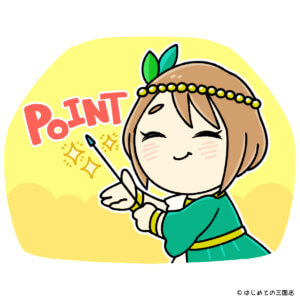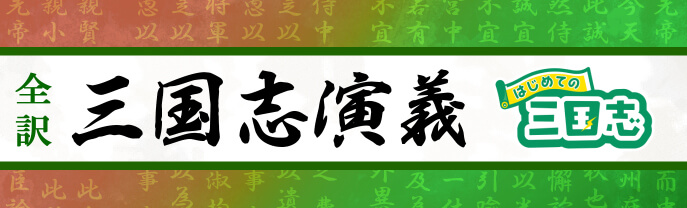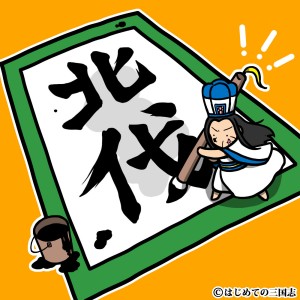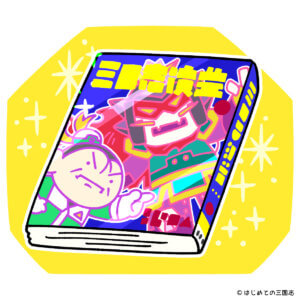三国志には、諸葛亮に『君は刺史くらいにはなれるだろう』と評された人物が出てきます。

この刺史というのは、現代で言うならば地方長官のような役割ですね。これを言われた友人たち、諸葛亮に「君はどうなんだい?」というと諸葛亮は何も答えなかったと言いますが……まあ、蜀の丞相になったので地位で言うならば彼らよりも諸葛亮は上になったと言えるのですが。
この諸葛亮に評された友人の一人こそが、諸葛四友と呼ばれる「孟建」です。この孟建、三国志演義では諸葛亮の友人というだけの扱いとなっていますが、その人物像、諸葛亮自身や、共に四友と称された徐庶との関係、更には諸葛亮に評された彼の能力や出世など、知れば知るほど大変興味深い人物です。三国志のメイン人物ではないものの、大変魅力的な孟建について、今回は解説をさせて頂きますね。
この記事の目次
三国志の孟建(公威)とは?まずは基本情報を解説
孟建(もう けん)、字は公威。生れは豫州汝南郡の人物です。三国志でも屈指の知名度を誇る諸葛亮の友人で、徐庶、石韜、崔州平と並べて諸葛四友と呼ばれています。彼自身は諸葛亮とは違い、魏に仕えることとなり、その優れた統治力を評価されました。『君は刺史くらいにはなれるだろう』と諸葛亮に評価された通り、涼州刺史から征東将軍にまで昇った人物です。
因みに魏では征東将軍には曹休や満寵といった人物が就任していますので、どれだけ重要であり、優秀な人物が付けられているのか、想像できるのではないでしょうか。
関連記事:満寵(まんちょう)ってどんな人?曹氏三代に仕え呉の天下統一を阻み続けた司令官
関連記事:満寵とはどんな人?裏の顔は泣く子も黙る拷問の達人【年表付】
孟建の荊州での遊学時代
そんな孟建ですが、有名な水鏡先生の学院塾で諸葛亮と出会い……という訳ではなく、それ以前から諸葛亮らと友誼を結んでいたようです。残っている記録によれば建安年間の初め、諸葛亮や徐庶らと共に荊州へ遊学したとあるので、この頃から彼らの友情は始まっていたと見ることができるでしょう。
諸葛亮だけでなく、徐庶、石韜も魏で任職を得ていますので、非凡な人物たちが集って問答をしていたのかもしれませんね。因みに「諸葛亮以外の三人は学問を精密に追求したのに対し、諸葛亮だけは大略を理解することに努めた」とあります。精密さではないものの大略、大要を見るに努めた諸葛亮、この頃から少し周囲とは違った見方をしていたのかもしれません。
関連記事:徐庶は魏に行ってから何をしていたの?
若き日の逸話|諸葛亮・徐庶・石韜との深い友情
ここで一つ、彼らとのエピソードをご紹介しましょう。
ある日のこと、孟建は故郷を偲び、北方へ帰ることを望みました。そんな孟建に諸葛亮は「中原には士大夫が沢山いる。遊び歩く場所は何も故郷に限らんだろう」と言って孟建を引き留めたとあります。要はこれ「中原に帰っても優秀な人が多くてお前なんか埋もれちゃうぜ!そんなの遊びに帰るようなもんだから帰らない方がいいぜ!」ってことなんですね、砕けた物言いにしますと。
これ、見ようによっては失礼ですが、逆を言うとそんな物言いができるほど彼らが親しく、遠慮のない付き合いができていたということになります。諸葛亮も孟建に故郷に帰ってほしくなかったんじゃないか……とか考えると、何だかこの頃の諸葛亮には一人の友人を思う若者の印象も受けられて、新しい一面には感じないでしょうか。実際これから諸葛亮以外の徐庶、石韜、そして孟建はずっと魏で一緒な訳ですが……ここではそれは置いといて、もう一つの有名なエピソードに移りましょう。
関連記事:徐庶は史実ではちゃんと出世していた!やっぱり仕えるなら魏の方が良いの?
関連記事:徐庶にはどんな逸話があるの?
諸葛亮が語った友人たちの評価
さてここで、改めて有名なエピソード「観人眼」についてお話ししましょう。諸葛亮は孟建、徐庶や石韜を「出仕すれば郡の太守や県の令、刺史くらいには至るだろう」と評価したエピソードです。実際に孟建は涼州刺史から征東将軍に、徐庶は荘郡の太守とほぼ同格である相に、石韜は太守から典農校尉にと魏で相応の地位に付いています。
これらのことから、諸葛亮の友人たちへの評価と彼らが付いたキャリアは、予見通りだったと言えますね。諸葛亮の非凡さ、友人たち自身の才能、これらが正しく嚙み合ったとも言えますが……諸葛亮はどうやら、これに対して一言あったようで……それについて、次の項で孟建のキャリアと共に紹介しましょう。
関連記事:諸葛亮孔明とはどんな人物なの?三国志初心者に分かりやすく解説
孟建の魏でのキャリアと功績、魏への仕官と順調な出世
諸葛亮が「刺史くらいにはなれるだろう」と評価した通り、孟建は涼州刺史に223年に就任します。残念ながら具体的な功績については記録されてはいないものの、この涼州刺史の頃に高い評価を受け、孟建は最終的により高い官位である征東将軍にまで昇進しました。
前述したようにこの官位は曹休や満寵が就任したこともある地位、魏で高く評価されていたことが分かりますね。余談ですが、孟建は涼州刺史に就任した223年は劉備が白帝城で没した年です。さてここでまでで諸葛亮の友人たちへの評価はずばり大当たりしていますが、その後、諸葛亮は北伐で孟建、石韜、徐庶らの官位を聞くと驚いて
「魏はそんなにも人材が多いのか。一体どうして彼らが用いられていないのか」
と嘆いたと言います。ただ諸葛亮自身の評価はこの時点で的中しているのですが……もしかしたら若き頃の諸葛亮と友人たちの評価であり、口にしないだけそれ以上にまで登れるだろう……と思っていたのかもしれません。何にせよ諸葛亮はここで魏の使者に「孟建に宜しく」と言葉を残しています。短いながら今だ友人たちへの思いを感じさせる話ですね。
関連記事:諸葛亮の性格は?人々の目から見た真実
【北伐の真実に迫る】
孟建に関するQ&A
ここで軽く、孟建に対するQ&Aに付いてお答えしていきましょう。
正史と三国志演義での違いは?
ここまでの記録は主に正史三国志にて、孟建について記録されたものです。では三国志演義ではどうかというと、孟公威の名で登場し、劉備が諸葛亮を探していた所で出会います。ここで石韜と共に諸葛亮の邸宅を劉備に教えますが、同行はしないまま……そうしてそれ以後は出てきません。この出番の少なさからか、石韜と共に孟建は三国志スキーの中でもかなり知名度が低い人物という扱いになってしまっているのです。
関連記事:『三国志演義』はいつ誕生したの?三国志演義の誕生について分かりやすく紹介
諸葛亮が北伐を行った時、孟建はどうしてた?
少し触れましたが、孟建はこの頃には涼州刺史となっていました。つまり、諸葛亮とは明確に敵同士という間柄になってしまっているのです。他二人も魏に仕えているのだから……と思うかもしれませんが、孟建だけは立場的に諸葛亮と対峙しかねない地位ですので、もしも対峙していたら別のドラマが生まれていたかもしれませんね。
それはそれとしてそんな時に魏の使者に「友人によろしく!」とかいう諸葛亮……割と公私は別と考えるタイプだったのでしょうか?
関連記事:【初心者向け】パリピ孔明から知る諸葛亮ってどんな人?5分でわかる三国志の天才軍師のガチすご伝説とは?
関連記事:蜀はなぜ北伐に乗り出したの?その目的は?
孟建はなぜ諸葛亮ほど有名ではないのか?
前述したように、三国志の知名度を上げる大きな要因である「三国志演義での出番の少なさ」が大きく影響しているでしょう。
比べると三国志演義で見せ場のある徐庶はかなり知名度がありますからね……その徐庶と比較すると「劉備に仕えていない」というのも一つの要因と言えるのではないでしょうか。
これで孟建が三国志の中心人物である曹操と個人的に親しくしたエピソードがあったり、もしくは後半で諸葛亮と相対する司馬懿と何らかの関係があればもっと知名度が……と惜しく思いますが、もうその時点では「諸葛亮と友人」は大きなエピソードではなく、話も割く状態でもなく……。孟建自体は経歴を見れば十分に優秀なのですが、やはり諸葛亮が故郷に帰ろうとした所を引き留めたように、どうにも人材が多すぎる魏では埋もれてしまった印象の方が強いですね。
関連記事:諸葛亮は苦手な兵法を克服していた!
諸葛亮とその四友、なぜ彼らは別々の道を歩んだのか?
さて諸葛亮とその四友、彼らはなぜ袂を別つことになったのでしょうか。魏で安定したキャリアを求めた?故郷がそもそも北方だったから?なんか劉備には仕えたくなかったという所感?
と、孟建の側から見るとどうにもはっきりと意図が見えて来ないのですが、逆に諸葛亮の側から見てみると、袂を別った理由が一つ思い浮かびます。それは「諸葛亮が魏を受け入れ難かった」のではないか?ということです。
曹操の最大の批難ポイントに、当時から「徐州大虐殺」というものがあります。そしてはっきりと記録されていないものの、嘗て徐州に住んでいた諸葛亮は、この曹操の行為が受け入れ難かったのではないでしょうか。
そうであるとするならば、袂を分かった理由は孟建ではなく、諸葛亮の方にあったのかもしれません。そうだとしたなら、嘗ての友人がその怨ある相手の国で、自分の想像通りに出世していくことを、諸葛亮はどう感じていたのでしょうか。そこにどのような感情があったのかどうかは分かりませんが、もしかしたら故郷に帰ろうとする親友を引き留めたのも……諸葛亮の一感情だった、のかもしれませんね。
関連記事:曹操の徐州大虐殺の真相には諸説あり?
関連記事:曹操はどうして徐州出身者に嫌われているのか?天下を狙うならやってはいけない「徐州大虐殺事件」の真相
三国志ライター センのひとりごと
さて、今回は主に諸葛亮の四友である孟建について色々とお話ししました。知名度こそ低いものの、その非凡さは間違いなく諸葛亮の友人であると言えるでしょう。そして諸葛亮という友人との道を別つとも、孟建も、そして徐庶、石韜も、更に諸葛亮自身もまた、己の場所を見定め、懸命に生きたのではないでしょうか。
と、ここで話は変わりますが諸葛亮の友人で、徐庶、石韜と並ぶ諸葛四友の一人、崔州平について少々。彼は孟建以上に記録がありません、というかほぼ0です。つまりは主だった人物に仕官せぬまま、歴史に諸葛亮の友人以外の記録を残してはいませんでした。
彼がどう生きたかは分かりませんが、筆者の個人的な意見を述べますと、彼らの師である水鏡先生のように、ただ好きな学問とだけ向き合い、小さな庵で生涯を終えていたらいいな……と思います。それは他の四人とは全く違う生き方ですが、それもまた、彼の人生として振り返ると輝いていたのではないでしょうか。
歴史にこそ触れられないままでも、己の生きる道を定めて生きた。諸葛四友にはそんなドラマを感じずにはいられませんね。どぼーん。
参考:蜀書諸葛亮伝 魏略
関連記事:司馬徽(しばき)はどんな人?なんでも善きかな、生涯誰にも仕えなかった偉人
諸葛孔明の兵法 「三国志」最強の軍師に学ぶ生存戦略・処世訓/三笠書房/守屋洋