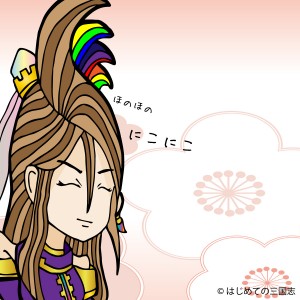後漢のラストエンペラー・献帝の皇后だった伏皇后。
三国志を彩る曹操(そうそう)・劉備(りゅうび)・関羽(かんう)・張飛(ちょうひ)らのように、三国志の序盤から献帝と共に登場し、行動している人物でもあります。
それでも登場は少なく、そして献帝の妻としての存在感も後から登場の曹皇后に押され気味・・・。
最大の見せ場はまさに最期の時。
皇后自ら曹操暗殺を企て、それがバレて殺されてしまいます。
この記事の目次
由緒正しい、皇后になるべく生まれたような女性
彼女の名前は伏寿(ふくじゅ)。
諸葛亮と同じ徐州瑯邪郡の出身で、
母親は後漢11代皇帝の娘。父親も名門の出で皇帝の娘婿として名高い・・・という由緒正しい血筋のお嬢様でした。
関連記事:魏や呉にもいた諸葛一族の話
辛酸を舐め続けた皇后
初平元年(190年)伏寿は、かの董卓が長安遷都を強行し、献帝を連れて行く際に貴人(という後宮の位)を賜ります。
続いて興平2年(195年)には皇后に立てられます。
新婚生活の最初からあの董卓(とうたく)の圧政と監視下での生活とは、うら若い伏皇后の心中は察するに余りありますね。
さらに苦境は続きます。
同年、献帝は洛陽へ帰還するため、多くの犠牲者を出しながら逃げるのですが・・・
時の皇帝の皇后である伏皇后や宮女達は歩いて逃げ、黄河を渡ります。歩きですって!
伏皇后の側近は逃亡中に斬られ、持っていた絹も奪われてしまい、伏皇后の衣服はその時に血にまみれ、安邑に辿りついた頃には献帝の服も穴が開いてボロボロに・・・。
命からがら逃げおおせた後も、しばらくは棗や粟を食べて生活する貧しい日々。
まもなく献帝が曹操によって庇護され、一応の皇后らしい生活には戻るのですが・・・
献帝達の周りは曹操の息のかかった者だらけ。
事実上は曹操が皇帝のようなものでした。
当時は政略結婚とはいえ、本来なら皇帝の妻、しかも皇后になることは女性として栄耀栄華のはず。
もちろん家柄・血筋から見ても、皇后になるにはふさわしかった彼女でしたが、皇后になった彼女は栄華を極めたとは言いがたかったのです。
関連記事:洛陽に続き、長安でも好き放題をした董卓
関連記事:菫卓が死んだ後、長安はどうなったの?
関連記事:1800年前の古代中国に鉄軌道跡を発見、燃料不足解消か?長安から漢中までの鉄軌道
関連記事:献帝を手にいれて、群雄から抜きん出た曹操
三国志演義における最期
そんな彼女が演義の中で再び大きく登場するのは、皮肉にも自身の最期。
三国志演義では先の曹操暗殺計画が失敗し董承(とうしょう)の一族が処刑され、その仇討ちとして伏皇后は父の伏完と共に曹操の暗殺計画を企てます。
その計画を献帝に提案した所、『今の宮中で最も信頼できる者』として宦官の穆順を紹介されるのです。
献帝も乗り気。
前回のクーデターは失敗したので、今回は絶対にしくじる事はできません。
伏皇后はこの穆順(ぼくじゅん)を信頼し、父・伏完への書簡を託し、計画のやり取りをするのですが・・・
関連記事:ブチ切れる献帝、曹操暗殺を指示
関連記事:呂伯奢一家殺害事件 曹操:「俺を裏切ることは許さない!」
曹操暗殺計画はまた失敗、その理由とは
密告によって既に動きを把握していた曹操に穆順が捕まり、計画も全て露見してしまいます。
忠義心に篤かった穆順は、誰に頼まれたのかどんな拷問にも口を割らなかったのですが、結局は伏完や伏皇后は逮捕されてしまうのです。
伏完・穆順一族はもろともに処刑され、二人の皇子も毒殺。
伏皇后は献帝の前で撲殺されるという非常に悲しい最期でした・・・。
もちろん言外に献帝に対しての見せしめの意味もあったのでしょうが、長く連れ添った妻を目の前で殺された献帝も悲しみます。
後漢書献帝伏皇后紀による最期
正史である『後漢書献帝伏皇后紀』での最期は少し違います。
同じように先に曹操暗殺計画を企てた董承が処刑された際、その娘で同じく献帝の後宮に入っていた董貴人が身重の身に関わらず処刑されたのを知り、伏皇后は父に曹操の排除を懇願します。
本来なら皇帝の子供を宿している貴人を処刑するなど、皇帝に刃を向けているのにも等しい事。
それを全く意にも介さない曹操に恐れをなしたといいます。
ところが父・伏完は娘の頼みを聞きながらも敢行する事はせず、建案14年(209年)に死んでしまいます。
過去に計画した曹操の暗殺計画が本人にバレてしまう
兄である伏典が跡目を継ぎ、曹操暗殺計画もそのまま闇に葬られたと思われたのですが、
建案19年(214年)になって突然、過去に伏皇后が曹操暗殺計画を立てていたことが露見。
曹操は激怒します。
もちろん曹操は献帝に伏皇后の『廃皇』を求め、皇后の印綬も取られてしまいます。
伏一族は処刑され伏皇后の生んだ2人も毒殺
伏一族は処刑され、伏皇后の生んだ2人の皇子達も毒殺。
伏皇后は独房に幽閉され、そこで死んだとされています。
さすがに曹操も民衆の手前、皇后を処刑するわけにはいかず、自殺を促したと言われています。
実質はお蔵入りしていた暗殺計画を蒸し返したのも、曹操は自分の娘を皇后に据えて皇帝の外戚として権力拡大をするのが狙いだったと見られています。
伏皇后の死の2ヵ月後には、曹操は献帝に嫁がせていた自分の娘を皇后に立后していることからも・・・言いがかりをつけて殺害したと推測されますね。
いつの時代でも、皇帝の外戚として力を拡大していくのは常套手段なんですね。
ところで伏皇后に頼まれても計画を敢行しなかった父・伏完と兄・伏典ですが、
先に董承の娘の最期も見ている身としては、敢行しない事こそが父親として兄として伏皇后と一族の身を守ることだと思ったのかも知れません。
実際、献帝伏皇后紀には父・伏完は『冷静で思慮深く心の広い人』と記され、
政治の実権が曹操にあると判断すると自分が皇帝の外戚の地位にあることを嫌い、自らが持っていた印綬を返上したと記されています。
既に宮中は曹操に牛耳られ、曹操に睨まれるのはどういう意味を持つのか分かっていたのでしょう。
三国志ライターAkiの独り言
伏皇后は周り人間達の思惑に翻弄された幸薄い人生だったと思ってしまいますが、献帝の傍らに皇后として仕え続けたのは実に20年。
夫婦でいえば、銀婚式まであとちょっと。
お互い夫婦としての情もあって、2人の皇子にも恵まれていて。
決して恵まれた人生では無かったと思いますが、それなりに幸せな時間があったのでは・・と思いたいです。
ならば、何故わざわざ暗殺計画など危ない橋を渡る必要があったのか。
由緒正しい生まれで長年献帝を支えた彼女の、漢王朝の皇后としての誇り高い矜持が曹操の横暴を許せなかったのかもしれませんね。
幸薄く影も薄い伏皇后ですが、儚いながらも最期まで誇り高い女性だったと思います。