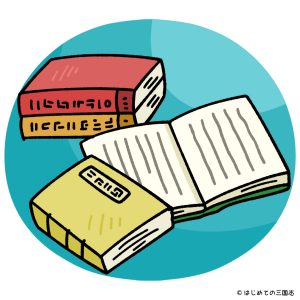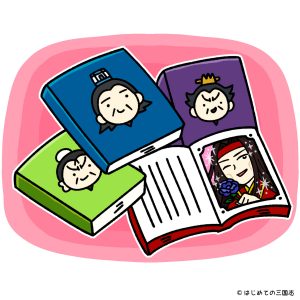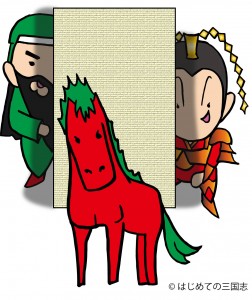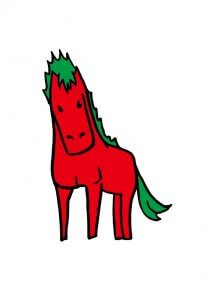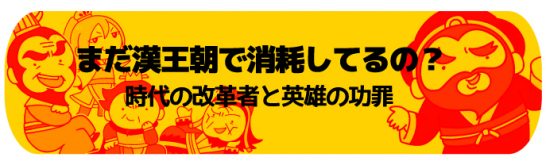『三国志』に登場する名馬……と言えば、多くの方がまず思い出すのが『赤兎馬(せきとば)』ではないでしょうか?
猛将呂布の愛馬として名を馳せ、後に関羽の愛馬となったという、
この『赤兎馬』、一体どのような馬だったのでしょうか?
関連記事:衝撃の事実!赤兎馬の子孫が判明!?
関連記事: 【痛恨の極み】吉川英治さん、どうしてあの三国志の迷シーンを復活させちゃったの?
赤兎馬は正史にも記録が残っている
『赤兎馬』の名前は正史『三国志』の他、
後漢王朝の歴史を記した『後漢書』にも、その名前を見出すことができます。
三国志の呂布伝によれば、袁紹に命じられた呂布が張燕を攻めた際に
『赤兎』と呼ばれた名馬に乗っていたと記されています。
また、呂布伝に引用された『曹瞞伝(そうまんでん)』には、赤兎馬が「人中に呂布あり、馬中に赤兎あり」と賞賛されていたといいます。
関連記事:6人の英傑を裏切り最後を迎えた呂布
赤兎馬の持ち主が入れ替わり続ける
『三国志演義』では、赤兎馬は「一日に千里を走る」稀代の名馬として描かれています。
『三国志演義』において、赤兎馬の最初の所有者は董卓でした。
董卓は呂布を養父である丁原から離反させるために赤兎馬を与え、呂布は丁原を自ら手にかけ、董卓の元に走ります。その後、呂布は曹操に討たれ、赤兎馬も曹操のものとなりました。
赤兎馬をもらった関羽は感激
曹操は自らの軍門に下った関羽を配下にしたいと考え、赤兎馬を与えます。それまでどのような贈り物をされても喜ばなかった関羽が、この赤兎馬を与えられたことについては大いに喜びました。
その理由を尋ねた曹操に、関羽は
『行方の分からない兄者(劉備)の居場所が知れた時、この赤兎馬ならどれだけ遠いところであろうとたちどころに駆けつけることができるでしょう』と答えました。
後に、関羽はこの赤兎馬を駆って劉備の元に参じます。
『樊城の戦い(はんじょうのたたかい)』で呉軍によって囚われた関羽が処刑された後、赤兎馬は呉の将軍であった馬忠に与えられましたが、馬草を一切口にしなくなり餓死したということです。
別記事:関羽千里行って有名だけど何なの?
赤兎馬の疑問点
『三国志演義』における赤兎馬の描かれ方で、まず疑問となるのは、その寿命です。丁原が呂布によって殺されたのが西暦189年のこと、関羽が死んだのが219年。赤兎馬は実に30年に渡って主を乗せ、戦場を駆け巡ったことになります。
現代の競走馬の寿命がおよそ20~30年程度と言われています。
これは現代の獣医学に基づく健康管理がなされた環境で生育されているウマの話です。
三国時代のウマがそれよりも長生きであったとは考えにくいことです。
呂布の『赤兎馬』と関羽の『赤兎馬』が同一の個体である可能性は低いといえるでしょう。(もちろん、フィクションである『三国志演義』の表記ですから、単なる誇張の可能性も十分にありますが)
むしろ、『赤兎馬』とはある一頭のウマのことではなく、『赤兎』と呼ばれる種類のウマであったと考える方が自然ではないでしょうか?
赤兎馬と呼ばれる馬の種類ではないのか?
古代中国では『ウサギのような顔をしている』ことが名馬の条件とされていました。
このことから、『赤兎馬』とは赤毛でウサギ(兎)のような
顔をしたウマのことであったと考えられます。
一方で、『赤兎馬』とは『汗血馬(かんけつば)』の事ではないかという見方も存在します。
『汗血馬』とは血のような汗を流して走るウマのことで、
中国においては古くから名馬の証とされてきました。
自然状態で汗腺(かんせん)から血が流れるということは考えにくく、
これは赤毛のウマなどが汗を流している姿が、
あたかも血の汗を流しているように見えたということを指しているのではないかと考えられています。
また、寄生虫の影響で実際に血の汗を流す場合もあるといいます。
寄生虫から受ける痛みやかゆみといった刺激に影響されて興奮状態になったウマが
狂ったように疾走したことが汗血馬の由来であるとする説も存在しています。
もう1つのユニークな説
汗血馬の正体に関する推測には、もうひとつ、ユニークな説があります。
それは汗血馬とはカバのことである、という説です。
カバは直射日光による乾燥や紫外線の影響から皮膚を守るため、
体表に赤みを帯びた体液を分泌しています。
これがまるで『赤い汗』のように見えることから、
汗血馬=競走用に訓練されたカバのことではないか……
という説が生まれたということです。
あの関羽や呂布がカバにまたがって戦場を駆けていた……
そんな光景を想像するとちょっと面白いですよね。
次回記事:いつまでやるの?またまた『赤兎馬=カバ説』を検証してみる。第2弾【HMR】
関連記事:三国志時代の通信手段は何だったの?気になる三国時代の郵便事情
関連記事:的盧は名馬なの?凶馬なの?劉備と龐統(ホウ統)の死