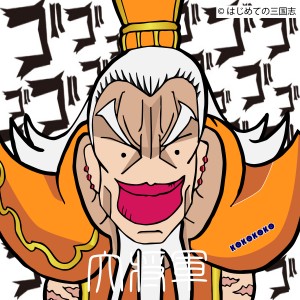酒。それは我々の生活に欠かせない嗜好品であり、人類共通の文化です。
しかもその製造工程の複雑さにもかかわらず、中国ではなんと4千年以上前の新石器時代からすでに酒が造られていました。
まだ冷蔵庫などない時代ですから、常温で放置された食べ物が自然発酵して、
その独特の味わいと「酔い」という不思議な現象が発見されたのだと考えられています。
魏の文帝・曹丕はワイン好き
果物の多い土地では、果物が自然に腐って発酵したところから果物酒が発明されたのでしょう。
ワインの発明も早く、シルクロードにあった康居という国では「蒲萄酒(ブドウ酒)」が名産でしたし(『後漢書』西域伝)
また魏の文帝・曹丕(そうひ)のワイン好きも有名な話です(『酉陽雑俎』)。
関連記事:そうだったのか!?曹丕はスイーツ男子。詩にスイーツの想いを込めちゃったよ!
関連記事:曹丕(そうひ)得意の詩で蜀の調理法を斬る
酒は理性を失わせる魔力
そして穀物が主食だった中国大陸では、穀物酒がメジャーでした。
「酒」という漢字は、酉の月(旧暦八月)に成ったキビから酒を造ったことが成り立ちといわれています。
しかしその字の意味は、「人の本性を善にも悪にもし、吉にも凶にもなるもの」(『説文解字』)。
酒には気分を盛り上げる反面、理性を失わせる魔力があることを、当時の人は認識していたのです。
このように酒に関して慎重であった古代の中国では、飲み方にルールがつくられました。
酒の席だからといって無礼講は許されず、むしろ無礼を働けばお手討ちになりかねませんでした。
関連記事:三国時代のお酒は発泡酒レベルだった?
春秋時代のお酒のマナー
春秋時代、君主主催の宴では酒は三爵(三杯)までで、それ以上は慎まなければなりませんでした(『春秋左氏伝』宣公伝二年)。
基準は不明ですが、三杯が適量ラインだったようです。
しかし爵は片手で包める湯呑みほどのサイズ。
当時の酒造技術ではアルコール度数はそれほど高くなかったという話がありますが、四杯以上で酔っ払い認定を受けたということは、
当時の人は酒に弱い体質だったのでしょうか。
関連記事:三国志を楽しむならキングダムや春秋戦国時代のことも知っておくべき!
三爵基準は三国時代にも残っている
ちなみにこの三爵基準は後の時代にも残っています。
たとえば東呉の周瑜(しゅうゆ)は音楽の上手で、“三爵の後”でも演奏ミスに気づいたといい(『三国志』呉書周瑜伝)、同じく呉の孫権は、酔い潰れたふりをして酌を拒んだ虞翻を手討ちにしようとして、別の臣下・劉基に「“三爵の後”に良き臣下を殺したとなれば世間からどう思われるか」と止められています(『三国志』呉書虞翻伝)。
実際に三杯飲んだというより、三杯を超えることが酒酔いの代名詞だったのでしょう。
関連記事:周瑜公瑾の輝かしい功績
関連記事:孫策と周瑜の怪しい関係は事実だったの?子不語にある逸話を紹介!
関連記事:三国時代の音楽ってどんな感じだったの?
他にも変わった飲みの文化
このほかにも、年少者は年長者が杯を空にしてからでないと飲んではいけなかったり(『礼記』)、
逆に年長者は、年少者のためにさっさと飲み干さないと「罰杯」といって罰の酒を飲まされたりしました(『漢書』叙伝注)。
現代の中華圏で「乾杯」と言って酒を一気飲みして盃を空にする習慣はここから来ているのかもしれません。
酒を飲ませることが罰として効果があるのかピンときませんが、春秋時代には実際に犯罪の刑罰として用いられました(『周礼』)。
また宴会には、酒を回し、会場の秩序を監督する「酒正」や「酒吏」という酒奉行がいました(『周礼』)。
彼らは宴会のルールであり、もし作法に反する者がいれば厳しく処罰され、誰も逆らえませんでした(『史記』齊悼惠王世家)。
関連記事:まったく安心できない三国志の全裸男、禰衡(でいこう)
関連記事:勝負下着の参考に!三国時代の下着ってどんなのだったの?
春秋時代と漢時代以降の飲みの文化
このように春秋時代の酒は形式的・儀礼的で、節度が重視されましたが、漢代以降には大衆化・風俗化し、呑兵衛が目立つようになります。
道端で酔い潰れて「酔龍」なんて大層な二つ名がついた後漢の名士・蔡邕や(『酒顛』)、前述の孫権も酒乱で有名です。
宴での飲み方もハデになり、参加者全員に酔い潰れるまで無理やり飲ませることもありました(『三国志』呉書孫皓伝、韋曜伝)
また飲み方も色々あって、たとえば青銅製の容器ごと火にかけて温めたり(「銅温酒樽」と刻まれた前漢の銅樽が山西省から出土しています)、三国魏では摘んだ蓮の葉に酒を注ぎ、簪で芯に穴をあけた茎をストローにして飲む「碧筒杯」なんて風流なものが考案されました(『酉陽雑俎』)。
しかし、酒の席のマナーは健在でした。
「酌」という漢字には、柄杓と同じ「勺」が含まれていますが、古代の宴会では床に敷物を敷いて座り、床に置いた大きな容器から別の道具で酒を「酌」んで杯に注ぎ入れました。この酌は主人役がすることも多く、主君が主催者であれば主君自ら酌をして回ったので、臣下はこれを受けなければ無礼とされました。
孫権(そんけん)が虞翻に対し激怒したのもこのためです。
「俺の酒が飲めねぇってのか!」というわけですね。
関連記事:権力者の重圧?酒癖の悪かった呉の孫権
関連記事:孫権の妻たちは意外と知られてない?
関連記事:孫尚香ってどんな人|孔明に曹操、孫権と並び評された人物
三國志ライター楽凡の独り言
いつの時代も、飲み会は楽しくもあり、付き合いや気配りなど厄介なこともあります。
ひとまずもし今後、泥酔して道端で目が覚めたら、「俺は酔龍だ」と叫んでみるのもありかも?
関連記事:1800年前に呂布がビーフバーガーを食べていた?気になる漢時代の食生活
関連記事:三国志時代の兵士の給料と戦死した場合、遺族はどうなってたの?