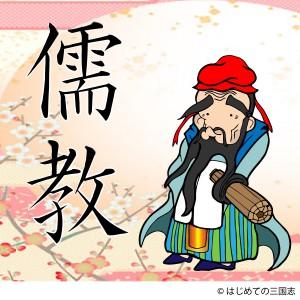数々の漫画やアニメ、ゲーム、ドラマや映画に至るまで沢山ビジュアル化されている三国志。その三国志でヒゲといえば、真っ先に思い浮かぶのは関羽雲長!
彼の黒く長く美しいヒゲ姿は、どんな三国志でもブレない関羽のトレードマーク。そうは言っても、激しい戦場を駆け回る武将なのにあんなに長いヒゲは邪魔じゃないのか?汚れないのか?蒸れないか?……ちょっと気になりますよね。
何故にそこまでヒゲを伸ばす必要があったのか?
今回はそんな三国志時代のヒゲのあれこれに迫ってみました!
この記事の目次
古代中国の道徳観念
三国志の時代である古代中国では、儒教の考えが道徳観念として浸透していました。それによれば、親からもらった身体は例え髪の毛一本たりとも粗末にしてはいけない、という教えがあったようです。カミソリをあてるなど言語道断!
そんな背景もあり、この時代の官僚は自分の道徳心をヒゲを生やすことで体現していた、という説があります。
関連記事:儒教(儒家)ってどんな思想?|知るともっとキングダムも理解できる?
関連記事:三国志の人々の精神に影響を与えた論語(ろんご)って何?
たなびくヒゲは男の証!
またこの時代の男性がヒゲに拘っていた大きな理由と思われるのが、宦官の存在です。
宦官は去勢をしている為に男性ホルモンが無くなり、ヒゲも生えなくなりました。また、宦官は去勢の為に親から貰った大切な身体を傷つけ、更には生殖機能を失ってしまい子孫を残す事ができません。
これは儒教的な考えの上では否定の対象でした。今でも中国では子孫を残さない男子は、ちょっと居心地の悪い思いをするようです。
また、出世の為に儒教の教えに背いてまで…といった批判もあったようです。実際に卑しい身分から、わざわざ出世の為に去勢をして宦官として権力を持った者も少なくありませんからね。
つまりヒゲが無い大人の男=宦官(普通の思考回路じゃない人)と思われる事が多かったのです。そんな背景もあるので、みんなヒゲをアピールし、自らが健常な男だという事を示す狙いがありました。宦官になんて死んでも間違われたくない!って事ですね。ヒゲは正真正銘、男の証だったのです。
関連記事:【キングダム ネタバレ注意】史上最悪の宦官 趙高(ちょうこう)誕生秘話
関連記事:人々の鑑になった良い宦官達
関連記事:後漢を滅ぼす原因にもなった宦官(かんがん)って誰?
関連記事:宦官VS外戚の争い 第二ラウンド
髪型よりもヒゲに気をつかえ!?
古代中国では、見た目が出世に影響する事が多々あったようです。ご存知、龐統(ほうとう)などは良い例ですね。孔明と肩を並べる(か、それ以上の)才覚がありながら、風采が上がらない、という理由で軽んじられていました。
ヒゲなどは象徴的で、君子ともなれば威厳を示す為にもヒゲは不可欠とされていたのです。老愛胡須少愛髪(ヒゲにこだわり髪はどうでもよい)といったような名言まであったそうですよ。
関連記事:的盧は名馬なの?凶馬なの?劉備と龐統(ホウ統)の死
関連記事:劉備入蜀の立役者、龐統の全戦歴
関連記事:龐統登場と同時に左遷(笑)
美ヒゲは1日にしてならず
そんな三国志の時代の男にとっては、無くてはならないヒゲでしたが、特に関羽は自分の自慢のヒゲのメンテナンスにも熱心なようでした。関羽が一時的に曹操の元に降った時のエピソードをひとつ。
曹操が関羽をもてなした際に、その立派なヒゲについて曹操が話題を振ったところ、関羽は
「秋にもなると500本はある私のヒゲも、3本、5本と抜け落ちます。その為に冬には黒い紗の布袋でヒゲを包み、抜け落ちないようにしています。」
と、答えたそうです。秋は抜け毛の季節。関羽のヒゲも切れ毛や抜け毛に悩んでいたようです。だから関羽はヒゲを袋に入れに入れて保護していたんですって。それを聞いた曹操は早速美しい綾錦でヒゲ袋を作らせ、関羽にプレゼントしました。
当時、関羽の気をひきたくて仕方なかった曹操は沢山贈り物をしていましたね。どれも中々気に入って貰えなく、ちょっと残念だった曹操も、ヒゲエピソードを聞いた時には「これだ!」と小躍りしたに違いありません。曹操が贈ったヒゲ袋はどんな物だったのか非常に気になりますが、さぞや絢爛豪華なヒゲ袋だった事でしょう。
関連記事:関羽に憧れていた新選組局長の近藤勇
関連記事:そんなカバな!!赤兎馬はカバだった?関羽は野生のカバに乗って千里を走った?(HMR)
関連記事:曹操のハニートラップ作戦が義に生きた武人・関羽に通用するのか?
関連記事:いつかは去りゆくと知っていながら関羽を厚遇した曹操
で、ヒゲ袋って何??
残念ながら(?)日本にはヒゲ袋なる文化は余り浸透してないようで、全く想像しづらいのですが、大辞林 第三版によると
あごヒゲを入れる布製の袋。両耳から紐でつる。
だそうです…。
て事は、日本でも使ってた事があるのかな?
そして、そんなヒゲ袋を着用した関羽。想像つきません…
『美髯公(びぜんこう)』の名付け親は献帝!?
先ほどの曹操とのエピソードの続きです。曹操から綾錦のヒゲ袋を贈られた関羽は、結構気に入ったらしく、翌日そのヒゲ袋を身につけて姿を現します。関羽の胸元に垂らされている美しいヒゲ袋に目を留めたのが献帝。
その場でヒゲ袋を外させたところ、ヒゲは関羽の下っ腹に届くほどの長さだったのです。それを見た献帝が思わず、
「まさしく美髯公よのう。」
と一言呟いたとか。それ以降、美髯公が関羽のニックネームの一つになりました。献帝、なかなかのネーミングセンスですね!綾錦のヒゲ袋も気に入ってもらえて、さぞや曹操も嬉しかった事でしょう。
関連記事:献帝(けんてい)とはどんな人?後漢のラストエンペラーの青年期
関連記事:献帝(けんてい)とはどんな人?後漢のラストエンペラーの成人期
関連記事:【後漢のラストエンペラー】献帝の妻・伏皇后が危険な橋を渡った理由!
関連記事:献帝を手にいれて、群雄から抜きん出た曹操
鬚と、髯と、髭の違い。
さて。ヒゲを表す漢字には『鬚』『髯』『髭』の3つがありますが、実はそれぞれ違いがあります。
『鬚』は、顎ヒゲ
『髯』は、耳のそばから頬にかけての頬ヒゲ
『髭』は、口ヒゲ
という区別があるのです。
関羽は、『見事な鬚髯をもっていた』と記されている事から、顎ヒゲ&頬ヒゲが美しく長かったという事になります。この区別を知ってると正史などを読む時に「ニヤッ」とする事ができますね!
関連記事:リアルな正史三国志の特徴って?ってか正史三国志は需要あるの?
関連記事:三国志は2つある!正史と演義二つの三国志の違いとは?
他にもいた!三国志ヒゲ自慢達
三国志には関羽以外にも特徴的なヒゲや、ヒゲの美しさ、長さについて演義や正史で言及されているヒゲダンディ達がいます。
【張飛(ちょうひ)】
燕頷虎須(アゴが張り虎のように威厳のあるヒゲ)
おなじみの虎ヒゲですね。実は正史には虎ヒゲといった記述はなく、演義での後付け設定なのですが、もはや虎ヒゲ以外の張飛は考えられない程に定番化。
【孫権(そんけん)】
碧眼紫髯(青い目に紫のヒゲ)
『呉書呉主伝注 献帝春秋』に記述。この紫髯は赤ヒゲという事らしいです。しかも寿命が長く、帝位に着く事ができる吉相だと言われていました。この紫髯という表現は胡人を表す時に使われたそうです。
【程昱(ていいく)】
身長八尺三寸、顎・頬に見事な髭を生やしていた。という記述が『魏書』にあります。ちなみに身長は現在でいえば約191cm。本当に太陽を支えられそうな高身長ですね。
身の丈七尺七寸、髭が立派な威丈夫と、『太史慈伝』にあります。身長は約180cmですかね。威丈夫とあるあたり、イケメンだったと推測されます。高身長のイケメンのヒゲは反則です!
三国志ライターAkiのひとり言
古代中国の時代にヒゲを伸ばさないのは、必ずしもマイナスイメージという訳でもなかった、とする研究家も居ます。それでも宦官に間違われるのが嫌だとか、威厳を表す為にヒゲを伸ばしていた人は多かったんじゃないでしょうか。
三国志演義でも人物の容姿の説明にはヒゲの描写が多い事からも、当時の男性にとってのヒゲは特別な意味合いがあったのだと思います。ワイルド感ですかねぇ。
ちなみに一般的に毛は1日に0.2〜0.3㎜伸びるそうです。
関羽は『身長九尺、髯長二尺(身長約210㎝、ヒゲ約45㎝)』
なので、約45㎝のヒゲに育てるまでには6年以上はかかっていた計算になりますね!そこまで時間をかけた自慢のヒゲなら、ヒゲ袋に入れて大切に保護したくなる気持ちもわかります。髪は女の命ですが、ヒゲは男の命だったんですね。